
そんなもん置いてけー!!
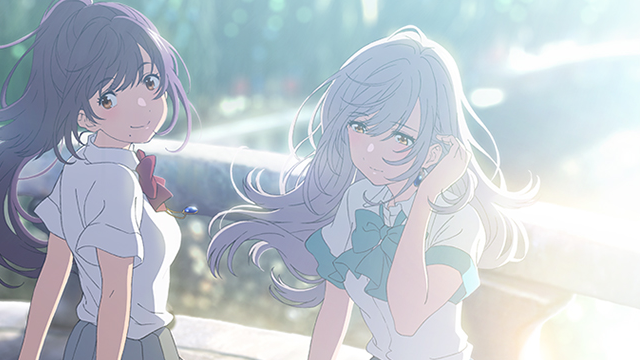
(主観的)あらすじ
色が見えるようになった瞳美の目はまたすぐ元に戻ってしまいました。
部室では何やら胡桃が落ち込んでいました。模試の成績が思わしくなかったようです。
胡桃は国立大学を志望していました。山吹は美大の写真学科を志望し、葵は就職するつもりだったのが絵を続けるために進学に変更。ふたりともやりたいことがあって進路を決めました。けれど胡桃が国立大学を選んだのは、ただ学費が安かったから。
胡桃にはお姉さんがいました。当初は国立大学に通っていたのに、自分でバイト代を貯めて、いつの間にか製菓学校に通いだし、さらには海外留学まで。胡桃はそんなお姉ちゃんに憧れていて、それでいて自分はああはなれないと考えていました。
魔法写真美術部のキャンプ、その最終日程に眼鏡橋での撮影会がありました。ここは長崎の夜景をバックに豪華客船が通る絶好のロケーションなのです。
ところが向かう途中でトラブル発生。事前に調べていた出航時間より早く船が出航していました。誰が見てももう間に合わないと思えましたが、この撮影会を楽しみにしていた深澤は諦めずに走りだします。続く他の部員たち。胡桃も深澤に呼ばれてやむなく走りはじめます。
結局船には間に合いませんでした。それでも深澤はなんだか妙に楽しそうです。彼のそんな姿を見て、胡桃も今の自分だけを見て将来の展望を打算的に考える必要なんてないのかもしれないと思い直すのでした。
瞳美も胡桃と同じことを考えました。
ずっと言いそびれていた色覚異常のことを、諸々の不安を振りきって、みんなに打ち明けることにするのでした。
写真趣味ってナンセンスだと思いませんか。
カメラなんて誰でもボタンひとつでそれなりに見栄えする写真を撮影できるものなのに、わざわざ知識や技術を磨いていこうとするなんて。
その労力にいったい何の意味があるんでしょう。いっそゼロから自分の手で描きあげていく絵画の方がよほどダイレクトに実力の向上を感じることができるでしょうに。たった一枚の写真、たった一瞬のシャッターチャンスを収めるために研鑚を重ねるこの業界、ともすれば素人の幸運なベストショットがプロを凌駕することすらままあるというのに。
はたして写真に一度きりの貴重な人生を費やす価値なんてあるのでしょうか?
・・・実際に人生をかけている人がいる以上、そこにはもちろん意味があるのでしょう。
写真であろうと、絵画であろうと、結局のところ当人にはわかる何かが。
葵の変化
「あのさ、これ。やっと見せられるものができたかなって」
葵の新しい絵は無数の色彩が散りばめられた、夢のある作品でした。
自然に果物、友人、雑貨、身の回りにあるあらゆるものをシャボン玉に閉じ込めて、まるでコラージュ作品のように全体としてのグラデーションを組みあげています。背景にはもちろん金色の魚の姿も。
そして中心に置かれた主題は大海原へ進みゆく帆船と、それをつかもうとする誰かの右手。
テーマは「憧れ」とでも解釈するべきでしょうか。
美しいものへの憧れ。身の回りのたくさんのものへの憧れ。誰かが好きだと言っていたものへの憧れ。
それら様々なものへの憧れに、これからもっともっと手を伸ばしていきたいというポジティブな意志を感じます。
瞳美の瞳を収めたシャボン玉が、彼にとっての個人的な憧憬の象徴であった金色の魚の上に描かれているあたりにキュンキュンしちゃいますね。
瞳美はなんだかんだでニブい子なのでその意味に気付かないでしょうが、いや、琥珀とかそのあたりに見せたら一瞬で気持ちがバレちゃうでしょ、コレ。大丈夫? 文化祭にこんな小っ恥ずかしいものを出展する気?
瞳美がキラキラした目で絵を見てくれるというのは彼にとってとても大きな救いとなりました。過去の栄光に追いすがるばかりでなく、今自分の絵を楽しみに待ってくれている人の期待が、今の彼のモチベーションを支えています。
「色が・・・。たくさんの色が・・・」
この感想を聞きたいがために、彼はこういう題材を選びました。
彼女を喜ばせたいがために。
彼女のおかげで変われた自分を見てもらうために。
「月白のおかげだ。魔法効いた。ありがとう」
アクセル
「そっちは? 受験で作品を提出しなきゃいけないんだろ」
「まだ。それまでにはもっとうまくなってるだろうし」
「進学決めたんだな」
「まあ。国立なら学費も自分である程度なんとかできるし。絵もちゃんとやってみようと思って。見てくれるやついるから」
山吹は元々前向きな人間ですし、葵の方も前回のことで顔を上げました。
ふたりそれぞれやりたいことも選んだ進路も違いますが、進学に明確な目的を持っている点で同じです。
「てか国立狙いなんスね」
「学費安いからね」
「それだけ?」
一方で胡桃はそういうものを持っていません。
今打ち込んでいるものといえば写真ですが、プロを目指している人たちほど本気でやっているわけではありませんし、そうなるといよいよこれといって大学選びの決め手となるものがありません。別にドケチ根性からというだけではなく、本当に学費くらいしか進学先を決める基準がないんです。
私もそうでしたね。これといって学びたいこともなりたい職業もなかったので、国立かつ自宅から通える距離(かつ二次試験に小論文がない)、という選択をしましたっけ。
「まあお父さんに高い留学費用まで出してもらってパティシエになったんだし、これくらいはね」
「お父さんよくボヤいてたよね。せっかく国立入ったのに、お姉ちゃん急に留学したいって言いだして。こっそりバイトもして製菓学校も通ってたし」
「いやー。お父さん説得するためにあの手この手使ったよね。懐かしい」
ところで胡桃には尊敬する人がいました。お姉ちゃんです。
自分のやりたいことを見つけて、そのためなら何でもして、なにより、一生懸命で楽しそうで。
「・・・なんで撮るの?」
「いい顔してると思って」
あくまで補助的な演出なので押さえておく必要はないのでしょうが、この運転中のシーンで不意にお姉ちゃんの足元のカットが挿入されます。
ゆっくりアクセルを踏み込む右足。
胡桃にとって、お姉ちゃんはグイグイ前へ進んでいく人でした。
これに対応するのがキャンプ中、胡桃が深澤と一緒にお姉ちゃんの話をしているシーン。こちらでは胡桃の手元のカットが挿入されています。
蛇口を閉める右手。
胡桃にとって、自分はその場で立ち止まる人間でした。
「胡桃も好きなことやりなよ。お父さんが反対しても私が味方するから」
「・・・うん」
そんなこといわれても。
そもそも胡桃にはお姉ちゃんのようにどうしてもやりたいことなんてありません。
「好きだから、夢だからって、それだけでどんどん前に進んでいけるんだよね。そういうのうらやましい。いいよね、本気になれるって。私にはそこまで好きになれるものなんてないから」
「やりたいことないんだ、私。だから勉強も身が入らないのかもね」
自分には無いものを持っているからこそ、尊敬しているんです。
「知ってる? 山吹と葵の進路。山吹はカメラ好きだから写真学科のある美大に行くんだって。葵は私と同じで国立狙いらしいけど、前より真剣に絵描いてる気がするし、何かあったのかな。ふたりともなんかお姉ちゃんと同じ顔してる」
それはお姉ちゃんだけの特別なパワーではなくて、周りを見渡してみれば山吹だとか葵だとか、お姉ちゃんみたいに前を向いて歩みをはじめている人たちは他にもいて。そういう人たちを見ているとなんだか、むしろ自分だけが特別にダメな人間であるかのような気がしてきます。
「いいよね、大人のお姉さん。モデル頼めない?」
「ダメー。お姉ちゃん忙しいから」
「ちぇ。しょうがないからクルミっちで我慢しとこっかな。――よく見たら、似てるような似てないような」
このお調子者の後輩はなんてことを言いだすんでしょうか。そんなはずあるわけがないのに。お姉ちゃんに失礼です。よりにもよってこんな自分なんかと一緒に見られるだなんて。
「・・・似てないよ、全然」
ダッシュ
「いいよね、本気になれるって。私にはそこまで好きになれるものなんてないから」
「写真は? 好きじゃないんですか?」
「好きだよ。でも、山吹みたいに詳しくないし、千草より撮るの下手だし。――私のは趣味で続ける程度の“好き”だよ」
“好き”って、そういうものでしょうか?
たしかに本気で好きならどんどん突き詰めていくものでしょうし、そうしたら自然と人並み以上の特技として身についていくものなのかもしれません。
おそらくは胡桃も覚えがあるでしょう。たぶん写真のことになんてそんなに興味がなかった頃と比べて、写真を好きになった今では雲泥の差ともいえるような技術が身についているはずです。山吹や深澤ほどうまくはないにしても、そこらのスマホのカメラしか触ったことのないような人と比べたら、さすがに胡桃の方がずっと魅力的な写真を撮れるはずです。
写真業界なんて狭き門。もちろんその程度じゃ仕事にしていくのは実際難しいのかもしれませんが。
だとしても。
「先輩はなんで絵を選んだんですか?」
「そんなカッコいいものじゃないよ。今も先のことを考えると怖くなる。“自分には絵しかない”とか、そういうすごい人にはなれないから。――描いて、描いて、描いて、とにかく描いてたら何か見つかるんじゃないかって。好きだから」(第6話)
“好き”って、そういうものだったでしょうか?
力量的に優れていることと好きであることの度合いはイコールだったでしょうか?
写真をはじめたばかりでヘタクソだった頃は今と比べてそんなにも好きな気持ちが少なかったでしょうか?
たとえば、葵がずっと引きずっていた子どものころの絵なんて大したものじゃありませんでしたよ。年齢相応、大胆なテーマの取り方に見るものがあるにしても、小学生らしい絵の枠を超越するほどのものではありませんでした。単純に芸術作品としての出来で語るなら、さすがに現在の葵の絵の方が完成度は高いです。
でも、小学生のころの葵と、ちょっと前までの葵、どちらがより絵のことを好きだったかといえば・・・それはもちろん小学生の葵ですよね。
不意に汽笛が鳴ります。
深澤の計画していた豪華客船の撮影会がご破算になろうとしています。
それは彼の写真を愛する気持ちが足りなかったせいでしょうか? 日頃の浮ついた態度のとおり、本当は写真のことなんか好きじゃなくて、だからこんなことになってしまったのでしょうか?
「これもう間に合わない――」
「いや、走ればいけますって!」
「はあ? 荷物もあるし」
「そんなもん置いてけー!!」
いいえ。彼はこんなにも強い気持ちで写真を愛していました。
胡桃がお姉ちゃんのことを尊敬しているのはパティシエとして優れているからだったでしょうか?
いいえ。尊敬するようになったのは彼女がまだ学生だったころ。夢に向かってまっすぐ努力していく姿に憧れの気持ちを抱いたのでした。力量なんかじゃなくて、その熱い夢にこそ尊敬の念を抱いたのでした。
「“好き”の度合いなんてみんな違うし、他にもっと好きなものできるかもしれないし、そんなの今すぐ決めつけなくてもいいじゃん。焦んなくても。大丈夫っスよ、先輩なら!」
深澤は走りました。ぶっちゃけ走っても結局間に合いませんでした。
それでも、彼が写真に対する情熱を持っていることを疑う人なんていないでしょう。“好き”とはつまり、そういうものです。
うまくいかないときは余計なことを考えてしまいがちなものです。
前話でせっかく色が戻った瞳美の目、なのにまたすぐ色が失われてしまいました。何か自分に原因があるのでしょうか。自分には色を見る資格なんてないのでしょうか。
「今を楽しく受け入れましょう。そうすれば、色づく世界があなたを待っています」
そんなの知ったこっちゃありません。今の瞳美が色のある世界を愛していることくらい、事情を知っている人からしたら明らかです。
前話の感想で書いたとおり、今色を取り戻してしまうと彼女にとってちょっとややこしいことになってしまうので、おそらくはそういうことを考えていたせいで再び色を失ってしまったんだと思うのですが――そういうのもともかくとして。
瞳美は色を見ることができませんが、色づく世界のことを愛しつつあります。
胡桃は山吹や深澤ほど写真がうまいわけではありません。
けれど、そんなの知ったこっちゃありません。それでも来海が写真を愛していることには変わりありません。部活中の彼女の楽しそうな顔を見れば誰にだってわかることです。
そう。いつも見ていてくれる人がいれば、自分の“好き”に自信を持つのにこれほど心強い味方はありません。
「月白のおかげだ。魔法効いた。ありがとう」
「絵もちゃんとやってみようと思って。見てくれるやついるから」
たとえば葵の場合は、それが瞳美でした。
「クルミっちスペシャルエディション。ほら、どれもいい表情してるでしょ。――何もなくたっていいんじゃない? こんだけいい顔できるんだから」
そして胡桃の場合は、それが深澤でした。
いつもくだらないちょっかいばっかかけてきて、いつも怒らさせてばっかりだけど、それだけいつも、彼はこちらを見ていてくれていました。自分でも気づいていなかった自分のなかの大きな“好き”を、彼はいつも見守ってくれていました。
「私も撮るよ! 千草よりいい写真撮る! 今は写真が一番だから!」
大好きな夢にまっすぐ突き進んでいくお姉ちゃんに憧れていました。
自分の“好き”はそこまでの“好き”じゃないから、お姉ちゃんみたいにはなれないと思っていました。
けれど、“好き”は“好き”でした。
この“好き”がこれからどういう未来へ向かっていくのかは想像もつかないけれど、胡桃は自分の好きなものにまっすぐ向かっていきます。まるでいつかのお姉ちゃんのように。

コメント