↑だいぶ強烈な読了目安時間が出ていますが、全体の5分の4くらいは後半にある生成AIとの対話ログなので、気楽に読んで大丈夫です。
これはそもそも何なのか
このキャラクターシートは、アニメ、マンガ、小説や映画などの登場キャラクターが、物語のなかでなぜそのように行動したのか、その背景にある動機や価値観を深く考察するためのツールです。
特に主人公など主要な登場キャラクターの言動には作品自体のテーマ性に直結しているものも多く存在するので、それらをひとつひとつ拾いあげることで作品をより味わい深く楽しめるようになります。
現バージョンをver.4.0とします。
基本的に私しか使わないはずのツールなので今までちゃんとした版管理をしてこなかったんですが、前回記事のものがver.3.2、『わんだふるぷりきゅあ』のキャラクターレポートに使ったものがver.3.5くらいに相当すると思います。
主な使い道
既存作品のキャラクター考察
登場キャラクターの行動原理や心理を、作中の描写に基づいて整理・分析します。
ウチのブログだと重要だと思ったセリフを書き起こして、それについて語るかたちで考察することが多いです。
「なぜこのキャラクターはこのシーンでこんなことを言ったのか?」「このときの行動の裏にはどういう思いがあったのか?」といった疑問を感じたとき、それを自分なりに解釈する手助けになるはずです。
演劇などで自分が演じる役のことを理解するためにも使えるでしょう。
オリジナルキャラクターの設計
一応、昔聞きかじった脚本のノウハウやTRPGのルールブックなどをいくつか参考にしてつくったので、小説などを書くときのオリジナルキャラクターをつくるのにも使えます。
特にキャラクターの内面を掘り下げたいときに強みを発揮します。
そのキャラクターの生い立ちや人間関係に始まり、どういう価値観や目標を持つようになるのかというキャラクターの人生というか歴史をつくりこむので、キャラクターの言動に一貫性を持たせることができます。
物語の表面には現れないかもしれない背景設定までつくりこめば、キャラクターはより生き生きと、自ずと”らしく”行動するようになるでしょう。
活用するのに向かないもの
現実に生きている人間を対象にすること
物語の登場人物は通常、作者によってある程度一貫した軸を持って設計されているものですが、現実の人間はもっと複雑で多面的な存在です。1つの軸(1つの人生の目的)の上だけで生きてはいません。
このシートは考察対象の言動の大半に一本の筋が通っていることを前提につくってあるので、これで生身の人間の内面を知った気になるのは非常に危険です。
作品外の知識ありきの考察
「このシーンは聖書のオマージュで~」とか「良くあるパターンだとこのキャラはたぶん父親を亡くしていて~」みたいな、いわゆる考察界隈で語られがちな根拠のない「考察」には対応していません。
このシートはあくまで国語の授業で習うような、しっかりとした根拠に基づく、基本に忠実な読解を目指します。
利用規約
もし使ってみたいと思うかたがいれば好きなだけ使用していただいて構いません。
著作者として私が利用者に遵守を求めるルールはクリエイティブ・コモンズ4.0 CC-BY相当です。
だいぶ前から日本語版ページが無くなっていて威圧感すごいですが、要はこのキャラクターシート自体をここ以外の場所で公開する場合、著作者の表示をしてください、というお願いです。
また、この記事へのリンクを添えるなどして一次著作者がこのブログ(の管理人)であることさえ明示していただければ、改変は自由に認めます。この「改変」には自分で記入したシートを公開する行為も含みます。
シートを使って自分が考察したことを前提に(作成したシート自体は公開せず)ブログなどの記事を書いたり、自分で設計したキャラクターを自分の小説などに登場させることなどに関しては一切制限ありません。そもそもそこにまで私の持つ著作権は及ばないはずです。たぶん。
ただし、あなたが考察に使ったアニメ、マンガ、小説や映画などの権利者との著作権トラブルについては私が介入するべきことではないので、そこは通常のファン活動や二次創作と同じように自己責任で対応してください。
その他、利用にあたって疑問点などあればコメント欄に書いてください。できるかぎり回答するようにします。
このシートを通じて作品とキャラクターの魅力をさらに深く探求し、考察を楽しみましょう。
具体的な使いかたについて
下にある13個のお題がここで紹介するキャラクターシート本体です。
これ以上でもこれ以下でもありません。適宜メモ帳でもWordでもExcelでも自分が使いやすいアプリにお題を貼って、それぞれ内面を知りたいキャラクターについて回答していくだけで考察が深まります。
ただし、回答のしかたにはちょっとした縛りがあるので、それをこれから説明します。
- A【こうなりたいと本気で目指す夢】(B+C+a1+a2)
- a1【尊敬もしくは軽蔑している人】(b1+b2+c1+c2)
- a2【自分の好きなところ】(b3+b4+c3+c4)
- B【絶対に諦められないもの】(b1+b2+c3+c4)
- b1【誰の役に立ちたいか】
- b2【誰に支えられているか】
- b3【嬉しかった想い出】
- b4【傷ついた記憶】
- C【努力する理由】(c1+c2+c3+c4)
- c1【みんなに広めたい思い】(b2+b3)
- c2【許せないと思うこと】(b1+b4)
- c3【感性が鋭くはたらく対象】(b1+b3)
- c4【自分でやりたいこと】(b2+b4)
項目の並びと役割
A,B,C(大項目)
各グループの先頭にある大文字のA,B,Cは、キャラクターにとって核心となる、特に重要な要素です。この3つを見出すことがこのシートの最終目的です。
Aはキャラクターが劇中で最終的に目指すことになる理想像や目標です。時系列的には一番最後に出てくるはずですが、キャラクターを一番よく象徴する要素なので読みやすさ重視で先頭に置いています。
たとえばプリキュアシリーズだと、最終決戦におけるラスボスとの思想戦で語られるやつです。
Bはキャラクターの基本原則です。大抵の場合、保守的な一面になります。
たとえばプリキュアシリーズだと、初めて変身するときの決意にあたります。
Cは物語の途中でキャラクターの心に新たに芽生える思いを表します。大抵の場合、進歩的な一面が強く表れます。
たとえばプリキュアシリーズだと、新技を習得するときなんかによく描かれます。
a,b,c群(小項目)
各グループの後ろにつづく小文字のa群,b群,c群は、大項目A,B,Cを個別具体的に掘り下げる項目です。
b1~b4では主に原体験とそれに由来する自信やトラウマを掘り下げます。
c1~c4では対人関係と自己認識の両面から現在の不満や行動原理を見出します。
a1~a2はb群とc群の内容を踏まえ、キャラクターがどうしてAの夢を持つに至ったのかの道筋を考察します。
記入のポイント
関連づけのルール
たとえば項目Aの後ろに(B+C+a1+a2)という標記がありますが、これは「カッコ内にある項目全てを踏まえ、しっかりと関連させた内容を記入してください」という指定です。
これがこのシートの最大の特徴であり、難しいところであり、強みです。
これは各項目が単なる思いつきの羅列に留まることを防ぐための措置です。「なぜそう思うのか」「その価値観はどこから来たのか」といった背景を想像しながら書き進めてください。
各要素を複雑に関連づけさせることで、キャラクターの思考に一貫性を見出しやすくなる効果も期待しています。
b1~b4だけ関連づけの指定がありませんが、これはこの4項目が原体験についてのものであり、他の全ての思考や感情の出発点として位置づけているためです。
(以前のバージョンではここにも関連づけの指定があったんですが、正直書きにくいだけでした)
記入順
関連づけの順序があるため、このシートは下にある順序で書き進めることになります。
慣れてきたら(Bをc1~c4の後で考えるなど)多少並びを前後させることも可能でしょう。
b1~b4(原体験)
↓
B【絶対に諦められないもの】
↓
c1~c4(対人関係と自己認識)
↓
C【努力する理由】
↓
a1~a2(夢への道筋)
↓
A【こうなりたいと本気で目指す夢】
各項目の書きかた
項目を埋めるためのヒント
各項目を記入する際は、まず結論を最初に書き、その後に詳しい説明や背景を続けると、内容が整理されて読みやすくなるでしょう。
このシート自体の構成も、結論(A,B,C)を先に示すかたちにしてあります。(実際にはb群やc群を先に書くのにね)
ウチのブログのアニメ感想文では最初に書く結論の代わりにセリフの書き起こしを載せている場合もあります。
これはまあ、そうしたほうが読んでくれている人が楽しみやすいだろうという下心ですね。
根拠となるセリフを記録することで考察の説得力も増すかもしれません。知らんけど。
もしかしたらいくつか意味合いが似ているように感じられる項目もあるかもしれません。
仮にそうであっても、できるかぎり全て違う内容について記述することを目指してください。多角的な視点で考察したほうが、そのキャラクターへの理解がより深まります。
項目ごとに異なる(○+○)の関連づけ先を意識すれば、それぞれの項目のニュアンスの違いが多少はわかりやすくなるかと思います。
※ 記入例1(参照先の記事のキャラクターシート自体は旧版)
【誰の役に立ちたいか】
父親の無念を晴らし、母親を心から喜ばせてあげたい。
ヒイロは遅く生まれた子どもだった。父オルテガが勇者として旅立ったとき、ヒイロはわずか3歳。
父との想い出はほとんど残っていないが、まるでお祭りのような大声援に送られて旅立っていったことは今でも鮮明に覚えている。
ヒイロにとって、父親とはそういう誉れ高い人だ。
父の訃報が届いたとき、使命を果たせなかったことを責める者はアリアハンにひとりもいなかった。ただ、誰もが悲しんだだけだ。
特にヒイロの母親は深い悲しみに暮れ、昼のうちから酒場に入り浸る日々が数年間続いた。ただし、そんな母も子育てに手を抜くことだけは絶対にしなかった。剣の道場から帰る夕方、アルコール臭い母が毎日温かな食事と必死の作り笑顔で出迎えてくれたものだった。
※ 記入例2(参照先の記事のキャラクターシート自体は旧版)
【誰に支えられているか】
「リードをつけるといろはを近くに感じるワン。いろはと一緒にいるこむぎは、ずーっと楽しくて、嬉しくて、ワンダフルなんだワン!」(第5話)
こむぎはいろはが大好きです。どうしてそんなに好きなのかっていったら、いろはがいつでもこむぎを好きでいてくれたからです。
どんなにワガママを言っても嫌いになったりなんかしない。どんなに忙しそうでも毎日時間をつくって遊んでくれる。だから、こむぎはいつも安心できていました。
あえて嫌な言いかたをするなら、いろははこむぎにとってとても都合がいい存在でもありました。物語が始まった最初のころは、だから、いつかいろはが遠くに行ってしまったらどうしようって漠然とした不安を抱いていました。色々お手伝いして、役に立つ存在だと思ってもらって、いろはのことをつなぎ留めたいと思ったことすらありました。
そのくらい、今も昔も、こむぎはいろはのことが大好きです。
A系統の考えかた
- A【こうなりたいと本気で目指す夢】(B+C+a1+a2)
- a1【尊敬もしくは軽蔑している人】(b1+b2+c1+c2)
- a2【自分の好きなところ】(b3+b4+c3+c4)
A【こうなりたいと本気で目指す夢】(B+C+a1+a2)
このキャラクターが物語の最後にたどり着くべき理想の姿や達成したい目標です。多くの場合、作品自体のテーマ性とも深く関わります。
物語のなかで成長したキャラクターにとって、最終的に自らの意志で物語を動かしていく原動力となります。
B【絶対に諦められないもの】を守るべき理由であり、C【努力する理由】によって何かを変えなければならなかった理由でもあります。
a1【尊敬もしくは軽蔑している人】を道しるべとした先にあるものでもあり、a2【自分の好きなところ】として今まさに叶えはじめていることでもあります。
キャラクターにとっての「最高の幸せ」とは何か、考えてあげてください。
a1【尊敬もしくは軽蔑している人】(b1+b2+c1+c2)
キャラクターの価値観や行動に最も大きな影響を与えたキーパーソンです。
人生の師。最高の親友。運命的に出会った恋人。あるいは命がけで殺しあったライバルかもしれません。
そのキーパーソンのどういうところが、なぜキャラクターの心を強く揺さぶるのか、というところまで具体的に記述してください。
この項目はそのキーパーソンとの関係性を通して、このキャラクターが「自分の外側にある世界とどう接していきたいのか」を掘り下げます。
b1【誰の役に立ちたいか】は「どういう相手と関わりたいのか」として、b2【誰に支えられているか】は「過去どういう人の助けを受けたのか」として、c1【みんなに広めたい思い】は対人関係における「ポジティブな働きかけ」として、c2【許せないと思うこと】は「ネガティブな拒絶反応」として、それぞれこのキャラクターの対人関係におけるスタンスを読み解くヒントになります。
a2【自分の好きなところ】(b3+b4+c3+c4)
キャラクター自身が最も気に入っている自分らしさのことです。
人は自分が一番理解できているという自負があるもの、もしくは一番深く探求したいと思った興味の対象に、一番強い愛情を注ぐものです。だから一番自分らしいと感じるところこそが、このキャラクターにとって一番の自己肯定感の源泉となります。
この項目はキャラクターが自分自身の内面とどう向き合ってきたかの歴史を反映します。
b3【嬉しかった想い出】は「好き」の基準となり、b4【傷ついた記憶】は「嫌い」を理解するための鍵となり、c3【感性が鋭くはたらく対象】は「弱さや不安」を知るきっかけとなり、c4【自分でやりたいこと】は価値観と行動原理が一致しているかどうかを占う手がかりとして、それぞれこのキャラクターがどのように自分を理解してきたかを振りかえるヒントになります。
B系統の考えかた
- B【絶対に諦められないもの】(b1+b2+c3+c4)
- b1【誰の役に立ちたいか】
- b2【誰に支えられているか】
- b3【嬉しかった想い出】
- b4【傷ついた記憶】
B【絶対に諦められないもの】(b1+b2+b3+b4)
キャラクターにとって「これを失ったら自分ではいられなくなる」と感じるほど大切なもののことです。
ものであったり、人であったり、想い出であったり、プライドであったり、ありかたは様々です。いずれにしろキャラクターのアイデンティティの根幹に深く関わります。
これを守る、あるいは取り戻すための戦いは受動的なものになるので、必然的に事件に巻きこまれたばかりの物語序盤によく発生します。
b1【誰の役に立ちたいか】やb2【誰に支えられているか】といった対人関係、b3【嬉しかった想い出】やb4【傷ついた記憶】といった個人的な経験の双方で、特別に大切なものは複合的に見出されるものでしょう。
b1【誰の役に立ちたいか】
キャラクターが貢献したい、守りたい、助けたいと願う対象のことです。
自立した大人であれば、守るべき家族や、仕事のクライアントなど、地に足ついた話になりやすいでしょう。
まだ何かを為す力を持たない子どもであれば、将来的に守れるようになりたい身近な人だとか、スーパーヒーローになって助けてみたい不特定多数の市民だとか、願望ベースでの話になるかと思います。
b2【誰に支えられているか】と対象人物が重複しやすい項目ですが、ボーイミーツガール系などヒロインとの密接な関係性が物語の核になる作品以外ではなるべく分けて考えたほうがいいでしょう。
b2【誰に支えられているか】
キャラクターが主に精神的な支えとして慕っている存在のことです。
主に保護者や、ペット、家族同然の絆で結ばれた仲間などが当てはまるでしょう。
生きものに限らず、座右の銘にしている言葉や、特定のコミュニティへの帰属意識といった概念である場合もあるかと思います。
b3【嬉しかった想い出】
キャラクターがかつて経験した、最も幸せな体験のことです。何が、どうして嬉しかったのかという部分に個人的な価値観が表れるでしょう。
基本的には物語開始前のエピソードを挙げることを推奨しますが、たまにそういった描写が一切ない作品もあるので、その場合はストーリー中の出来事から拾ってください。
b4【傷ついた記憶】
キャラクターのトラウマやコンプレックスを生んだ、辛い経験のことです。複数人で同じ経験をしたとしても、それぞれの感性次第で心に負う傷のかたちは千差万別になるはずです。
作風や対象年齢によっては物語開始前どころかストーリー中ですらそれらしい描写が出てこないことがあるので、その場合は葛藤シーンだとか、苦戦したバトルシーンから心理描写を抜き出してみるといいでしょう。
C系統の考えかた
- C【努力する理由】(c1+c2+c3+c4)
- c1【みんなに広めたい思い】(b2+b3)
- c2【許せないと思うこと】(b1+b4)
- c3【感性が鋭くはたらく対象】(b1+b3)
- c4【自分でやりたいこと】(b2+b4)
C【努力する理由】(c1+c2+c3+c4)
キャラクターが現状に甘んじることなく、何かを変えようと行動を起こすときの動機のことです。
B【絶対に諦められないもの】が「現状を守る」という受動的な側面を持つのに対し、こちらは現状に不満を認め、新しい何かを創り出そうとする能動的な意志を表します。
現状をよく理解していることが前提になる話なので、どちらかというと物語中盤~終盤によく発生する展開です。
変えたいものと変えたくないものは同時に存在しうるので、時系列的にもB【絶対に諦められないもの】と両立することはありえます。
c1【みんなに広めたい思い】やc2【許せないと思うこと】といった他者への働きかけのスタンス、c3【感性が鋭くはたらく対象】やc4【自分でやりたいこと】といった自分のなかにある衝動への理解の、両方の視点を総合して考えてください。
c1【みんなに広めたい思い】(b2+b3)
キャラクターが周囲の人々や社会に対して共有したい、実現したいと願う主張や希望のことです。
基本的にはポジティブなメッセージになるはずですが、他人の考えかたへの干渉を伴うので、ときに人間関係への不和をもたらします。
b2【誰に支えられているか】は支えてくれた人からの学びや感謝が基本思想に結びつくため、b3【嬉しかった想い出】は成功体験から来る自信の醸成につながるため、関連づいています。
c2【許せないと思うこと】(b1+b4)
キャラクターの正義感や倫理観に反し、ひときわ強い怒りや義憤を呼ぶものは何かという論点です。
他人の言動を積極的に否定しようとするネガティブな行為である以上、正しいことであろうとなかろうと相手との関係性は大抵悪化します。それを覚悟のうえで表明せずにいられないほど、このキャラクターにとっては強いこだわりということになります。
b1【誰の役に立ちたいか】で何者からその人を守ろうとしたかという視点、b4【傷ついた記憶】からの反省を踏まえて何を拒絶したいと思うかという視点に、それぞれ関連づいています。
c3【感性が鋭くはたらく対象】(b1+b3)
キャラクターが人一倍敏感に反応し、あるいは深く探求しようと思うものです。漠然と感じる「好き嫌い」とは若干意味合いが異なります。
美しいものや優れた技術、周囲の人が抱く特定の感情など、対象は様々。ただ、強い関心が向くということはそれだけ(自覚的、無意識的問わず)自分にとって欠けているものに対する羨望、あるいは強い脅威を感じているということでもあります。
悪問だということは重々承知なのですが、実はこれ、キャラクターの自己嫌悪を探るための出題です。それもc2と違って、他人のせいにして攻撃することでは解消できない類いのコンプレックスです。
b1【誰の役に立ちたいか】の根底にはその相手に自分の価値を高く評価されたい願望があるでしょうし、b3【嬉しかった想い出】は心のなかに現時点の自分では到底及ばない優れた理想像を定着させてしまうでしょう。そういった意味合いで関連づきます。
c4【自分でやりたいこと】(b2+b4)
キャラクターが「これは自分の役目だ」「自分が成し遂げたい」と主体的に認識している具体的な活動や目標です。
好き嫌いや得意不得意、他者からの期待、あるいは責任感など、動機は様々ですが、いずれにしろキャラクター自ら「やりたい」と思っているんだということが重要です。
b2【誰に支えられているか】を自覚することでこれまで自律的になれていなかった部分に気づき、b4【傷ついた記憶】を繰り返したくないという思いから能動的な行動力が芽生えます。
生成AIにこのキャラクターシートの有用性を聞いてみる
キャラクターシートの解説自体は以上です。
ここから先はオマケというかなんというか、生成AIを使ってこのシートの有用性を検証していくコーナーです。
ここまでの長ったらしい解説文のさらに4~5倍もある超長文が続くので、時間があるときに、何日かに分けて読むことをオススメします。
というわけで。
今回つくったこのシートがどのくらい使えるものか、どういうところに強みがあるか、改善すべきところはあるかなどについて、Gemini、ChatGPT、Claudeそれぞれの意見を聞いてみました。
こういう分野の研究ってアメリカ(というかハリウッド)で活発に行われているらしいんですよね。それ考えると、今の生成AIの学習元って英語圏のデータベースがメインのはずなので、もしかしたらそっち系の本まで網羅しているかもしれないと期待した次第です。
結果、大正解でした。
私から質問したこと
問1(このキャラクターシートについて解説させる)
下記は小説を書く際に登場人物の人間性や生い立ちなどを設計するために用いる設問群です。各行最初にある“A”や”b1″などは設問を識別するためのラベル、右隣の【】内にあるのが設問本文、その右にある(○+○)というのは「そこに書かれた複数の設問への回答を踏まえて考えなければならない」という指定、一番右は設問意図についての簡単な注釈です。
まず、登場人物を設計するうえで何故この設問群を考えさせるのか、全体の意図を推察したうえで、各設問にどういう狙いがあるのかそれぞれ記述してください。
人物名
A【こうなりたいと本気で目指す夢】(B+C+a1+a2)(物語の最終目的)
a1【尊敬もしくは軽蔑している人】(b1+b2+c1+c2)(一番影響を受けた人物)
a2【自分の好きなところ】(b3+b4+c3+c4)(一番深く自己洞察できている部分)
B【絶対に諦められないもの】(b1+b2+b3+b4)(依存している対象)
b1【誰の役に立ちたいか】(他人からの影響1)
b2【誰に支えられているか】(他人からの影響2)
b3【嬉しかった想い出】(個人的な原点1)
b4【傷ついた記憶】(個人的な原点2)
C【努力する理由】(c1+c2+c3+c4)(現状の何が不満なのか)
c1【みんなに広めたい思い】(b2+b3)(他人への干渉1)
c2【許せないと思うこと】(b1+b4)(他人への干渉2)
c3【感性が鋭くはたらく対象】(b1+b3)(個人的なこだわり1)
c4【自分でやりたいこと】(b2+b4)(個人的なこだわり2)
キャラクターのつくりかたについてなら脚本理論の本にいろいろ書いてあるのを知っているのですが、さすがにアニメキャラ考察用のノウハウなんてものはほとんど聞いたことがないので、話をスムーズに進めるためにここでは「自作小説用のキャラクタージェネレーターである」という前提にしてあります。
問2(作例を見たうえで改めて評価させる)
下記はこの設問群を用いた登場人物の作例です。
この作例が設問意図と適合しているか、そもそもこの設問群自体が登場人物設計において効果的に機能しているか、考えるべき設定に過不足はないかなど、評価してください。
(※ ゼノブレイドクロスDEプレイ日記の主人公として作成したキャラクター“ミルストレア”を作例として渡しました。3600字と結構なボリュームなので、読みたい場合は下記の記事を開いてください)
具体的な作例を渡したほうが生成AIも私がこのシートで何をしたいのか理解しやすいだろうと思っての措置です。
質問も私がこれに対する答えが欲しいというより、生成AI自身の理解を促すことを意識しています。
問3(他の脚本理論と比較してもらう)
広く知られている脚本術について理解はありますか?
それらの脚本術における登場人物設計手法と比較し、この設問群の強みや不足部分、あるいは重複している設問など洗練されていない点などを指摘してください。
これが本題。
ハリウッドの脚本術はかなり体系化が進んでいると聞いています。私のキャラクターシートも割とシステマチックなつくりなので、もし生成AIがそっちの知識を押さえているならいい感じの指摘をもらえるはずだと思っていました。
問4(改善案を作成させてみる)
以上の考察を踏まえ、設問群について具体なテンプレートで改善案を提示してみてください。
予想以上にちゃんとした知識を持っているようだったので、試しにここまでやらせてみました。
問5(キャラクター設計にかかる所要時間の予想)
初学者が最初に提示した質問群を用いて、作例「ミルストレア」程度の作り込みのキャラクター設計をゼロから行う場合、所要時間はどのくらいかかると考えますか?
最後におまけの質問。
参考までに、今回の作例をつくるのにかかった時間はおよそ3時間ほどでした。
ただしこれは私がある程度シートの扱いに慣れていることに加え、「大まかなストーリー展開を知っているゲームでロールプレイするための主人公設定」で完全にゼロから組み立てているわけではないため、そこそこスムーズに設計できた事例です。
私から見た各生成AIに対する雑感
Geminiはこのシートの最大の特徴である関連づけルールがいかに重要な役割を果たしているかに注目して、熱心に語ってくれました。
ところどころ質問からのオウム返しみたいになっている部分もありますが、全体的に多弁で情報量が多く、シートへの理解も深いです。私が書いた拙い解説ではピンとこなかった、という人には良い講師になってくれると思います。
ChatGPTははっきり言ってシートに対する理解度は浅っっっさいのですが、プレゼン能力がメチャクチャ高かったです。文章を読みやすくしようとする工夫がとにかくすごい。
特に、参考文献の紹介は一見の価値ありです。キャラクター設計を学ぶうえで適切な教材を、さらっと網羅的に紹介してくれています。ろくに勉強していない私ですらさわりの内容くらいは聞いたことがある、どれも超一流の超有名本ばかりです。バイナウ。
Claudeは今回初めて使ってみたんですが、びっくりするくらい読解力が高いですね。私の意図をほぼ完璧に読み取ってくれたうえで、独自の視点と独自の言葉で簡潔に評価・指摘事項を教えてくれました。
シートの改善案なんてすっごいんだから。私のキャラクターシートをベースにしたうえで、よりわかりやすく、より工夫を凝らした、より深く掘り下げられるシートをささっとつくってくれました。書くのにとんでもない労力がかかることにだけ目をつぶれば、たぶんこのまま使えるレベル。
以下、どれもめっちゃ長いので折り畳んであります。それぞれクリックして開いてください。
Geminiさんの見解
モデル情報:Gemini 2.5 Pro Preview 05-06
答1(このキャラクターシートについて解説させる)
この設問群は、登場人物に深みと一貫性を持たせ、物語の中で生き生きと行動させるための骨子を設計することを目的としています。単に性格や外見を決めるだけでなく、その人物が何を考え、何に突き動かされ、どのように他者や世界と関わるのか、その根源的な部分を多角的に掘り下げるためのものです。
(○+○)の指定は、各要素が独立したものではなく、相互に影響し合い、複雑な人間性を形成していることを意識させるためのものです。これにより、表面的な設定の矛盾を防ぎ、より説得力のある人物像を構築できます。
全体の意図推察
この設問群を考えさせる全体の意図は、以下の3点に集約されると推察します。
- キャラクターの行動原理の明確化: なぜそのキャラクターがそのように行動するのか、その動機や目的を深く掘り下げることで、物語における行動に一貫性と説得力を持たせる。
- キャラクターの多面性と深層心理の探求: 単純な善悪や性格付けではなく、過去の経験、他者との関係、内面的な葛藤などを組み合わせることで、人間らしい複雑さや深みを持ったキャラクターを創造する。
- 物語の推進力の創出: キャラクターの「夢(A)」、「諦められないもの(B)」、「努力する理由(C)」は、物語を動かす大きなエンジンとなります。これらの要素を明確にすることで、キャラクターが自律的に物語を牽引していく力を与える。
関連づけルールに着目しているぶん、行動の一貫性や人格の複雑さを分析するのに向いていること、A,B,Cが特に重要な意味を持っていることについて、他の生成AIよりも強く意識しているようです。
各設問の狙い
以下に各設問の狙いを記述します。
人物名
- 狙い: 設計する対象を明確にする基本的な項目です。名前の響きや意味合いが、キャラクターのイメージに影響を与えることもあります。
A【こうなりたいと本気で目指す夢】(B+C+a1+a2)(物語の最終目的)
- 狙い: 物語全体を通してキャラクターが追求する究極の目標、あるいは到達したい理想の状態を定義します。これが物語の縦軸となり、キャラクターの行動の大きな指針となります。
- (B+C+a1+a2)の指定から: この夢は、個人的な執着(B)、現状への不満や原動力(C)、影響を受けた人物への思い(a1)、そして自分自身の深い理解(a2)に基づいて形成されるべき、根源的で強いものであることを示唆しています。
a1【尊敬もしくは軽蔑している人】(b1+b2+c1+c2)(一番影響を受けた人物)
- 狙い: キャラクターの価値観、行動規範、目標設定などに最も大きな影響を与えた人物を特定します。その人物への感情(尊敬か軽蔑か)によって、キャラクターが何を肯定し、何を否定するかの基準が明らかになります。
- (b1+b2+c1+c2)の指定から: その影響は、他者への貢献意識(b1)、支えられているという実感(b2)、社会に伝えたいメッセージ(c1)、そして許せないという強い感情(c2)といった、他者との関わり方や信念の形成に深く関わっていることを示します。
a2【自分の好きなところ】(b3+b4+c3+c4)(一番深く自己洞察できている部分)
- 狙い: キャラクターの自己肯定感の源泉や、自分自身で認識している長所・特技を明らかにします。これはキャラクターの自信や行動の源となるポジティブな側面です。
- (b3+b4+c3+c4)の指定から: この自己肯定は、過去の良い経験(b3)だけでなく、困難を乗り越えた経験(b4、傷ついた記憶から得た強さなど)や、個人的なこだわりや得意分野(c3, c4)といった内面的な経験と洞察に裏打ちされていることを示唆します。
B【絶対に諦められないもの】(b1+b2+b3+b4)(依存している対象)
- 狙い: キャラクターが精神的に、あるいは物理的に強く依存し、失うことを極端に恐れる対象(人、物、信念、状態など)を明確にします。これはキャラクターの弱点や行動の制約、あるいは強い動機にもなり得ます。
- (b1+b2+b3+b4)の指定から: この「諦められないもの」は、他者への貢献欲求(b1)、他者からの支え(b2)、幸福な過去の記憶(b3)、そしてトラウマ的な経験(b4)など、他者との関係性や過去の重要な経験と深く結びついていることを示します。
b1【誰の役に立ちたいか】(他人からの影響1)
- 狙い: キャラクターの利他的な側面や、どのような対象に対して貢献したいという欲求を持っているかを明らかにします。社会的な立ち位置や他者との関わりにおける基本的なスタンスを示します。
- 注釈「他人からの影響1」から: 他者からどのような影響を受け、その結果として誰かのために行動したいと考えるようになったのか、その動機を探ります。
ここでb1に(他人からの影響1)という注釈をつけているのは、「この人の役に立ちたい」と思うようになるのは「そう思える人との出会いがあったから」もしくは「そう思えるような関係性を築いてもらえた」という受動的なつながりを前提にしているからです。
b群は原体験についての設問なので、基本的に受動的な視点で考えたほうが、その後の設問との関連づけもスムーズに進みます。
b2【誰に支えられているか】(他人からの影響2)
- 狙い: キャラクターが精神的、物質的に頼りにしている、あるいは感謝している他者の存在を明らかにします。これはキャラクターの安心感や帰属意識の源泉となります。
- 注釈「他人からの影響2」から: 他者からどのようなサポートや影響を受け、それがキャラクターの精神的な安定や行動の基盤になっているのかを探ります。
b3【嬉しかった想い出】(個人的な原点1)
- 狙い: キャラクターの価値観や幸福の基準を形成したポジティブな過去の経験を特定します。現在の行動や目標の原動力となる「光」の部分です。
- 注釈「個人的な原点1」から: 何がその人にとって喜びであり、何を大切にしているのか、その根源的な肯定体験を掘り下げます。
b4【傷ついた記憶】(個人的な原点2)
- 狙い: キャラクターのトラウマやコンプレックス、恐怖心の源泉となったネガティブな過去の経験を特定します。現在の行動の制約や、乗り越えるべき課題、あるいは強い反発心を生む「影」の部分です。
- 注釈「個人的な原点2」から: 何がその人にとって苦痛であり、何を避けようとするのか、その根源的な否定体験を掘り下げます。
C【努力する理由】(c1+c2+c3+c4)(現状の何が不満なのか)
- 狙い: キャラクターが現状に対して抱いている不満や問題意識、そしてそれを改善・克服するために行動する動機を明確にします。夢(A)へ向かうための具体的なエネルギー源です。
- (c1+c2+c3+c4)の指定から: この努力の理由は、社会や他者に対する提言(c1)、個人的な義憤(c2)、強いこだわり(c3)、そして自ら行動せずにはいられない衝動(c4)といった、内発的な強い意志に基づいていることを示します。
c1【みんなに広めたい思い】(b2+b3)(他人への干渉1)
- 狙い: キャラクターが他者や社会に対して積極的に伝えたい、共有したいと考えている価値観、信念、あるいは警告などを明らかにします。
- (b2+b3)の指定から: この「広めたい思い」は、自身が支えられた経験(b2)や、幸福な記憶(b3)から得た普遍的な価値や教訓に基づいていることが多いことを示唆します。
c2【許せないと思うこと】(b1+b4)(他人への干渉2)
- 狙い: キャラクターの正義感や倫理観の境界線を明らかにします。何に対して強い憤りを感じ、行動を起こすきっかけとなるのかを示します。
- (b1+b4)の指定から: この「許せないこと」は、誰かの役に立ちたいという思い(b1)が脅かされる状況や、過去の傷ついた記憶(b4)と関連する不正や理不尽さに対して強く反応することを示唆します。
c3【感性が鋭くはたらく対象】(b1+b3)(個人的なこだわり1)
- 狙い: キャラクターが他の人よりも敏感に感じ取ったり、特別に興味を引かれたりする物事や分野を特定します。才能や特技、あるいはフェティシズムに繋がることもあります。
- (b1+b3)の指定から: この鋭敏な感性は、誰かの役に立ちたいという対象(b1)への深い洞察や、過去の嬉しかった思い出(b3)と結びつく美しいものや心地よいものに対して働きやすいことを示唆します。
c3は設問自体がひねくれているので、他の生成AIも含め正しく意図を理解できなかったようです。
c4【自分でやりたいこと】(b2+b4)(個人的なこだわり2)
- 狙い: 他人に任せたくない、自分自身でなければ納得できないという、キャラクターの強い主体性やこだわり、あるいは責任感の範囲を明らかにします。
- (b2+b4)の指定から: この「自分でやりたいこと」は、支えてくれる人(b2)への責任感や、過去の傷ついた記憶(b4)を繰り返さないための強い意志、あるいはトラウマを克服しようとする個人的な課題と関連していることを示唆します。
これらの設問に答えていくことで、作者自身も気づかなかったキャラクターの側面が明らかになり、より魅力的で、物語を力強く動かしていける人物が生まれるでしょう。
答2(作例を見たうえで改めて評価させる)
この登場人物「ミルストレア」の作例について、設問意図との適合性、設問群自体の効果、設定の過不足の観点から評価します。
設問意図との適合性について
全体として、作例は各設問の意図を非常によく汲み取り、深く掘り下げられています。特に(○+○)で示された参照設問との関連性を意識した回答になっており、キャラクターの行動や感情に一貫性と多面性が生まれています。
- A【最終的に目指すことになる理想】: 「自分を大切にできる人」という目標は、自己嫌悪に陥っている現状(B, a2, b4で示唆される)からの脱却を目指すものであり、物語の最終目的として適切です。依存対象(B:心の平穏)、努力理由(C:他人を拒絶するため)、影響を受けた人物(a1:ヒメリへの羨望と尊敬)、自己洞察(a2:従順さ)が複雑に絡み合い、この理想に至るまでの葛藤や成長を描く余地を十分に含んでいます。
- a1【尊敬もしくは軽蔑している人】: ヒメリへの「羨望」と「尊敬」というアンビバレントな感情は、ミルストレアの自己評価の低さ(自分はヒメリのようにはなれない)と、他者への純粋な評価(ヒメリの努力への尊敬)を巧みに表現しています。b1(受動的な他者貢献)、b2(支えられている実感)、c1(寛容さへの願い)、c2(判断を迫られることへの嫌悪)といった要素が、ヒメリとの対比や彼女への感情の根源を示唆しており、設問意図に合致しています。
- a2【自分の好きなところ】: 「従順なところ」を挙げることで、自己肯定感の低さと、面倒事を避けたいという彼女の性格(b3:感謝される喜び、b4:自己への失望、c3:心配されることへの拒否、c4:自己犠牲的な行動)を巧みに表現しています。一見ポジティブな設問に対し、ネガティブな側面からアプローチすることでキャラクターの屈折した内面が際立っています。
- B【絶対に諦められないもの】: 「心の平穏」は、彼女の怠惰に見える行動様式(b1)やワーカホリックな側面(b2)、他者からの承認で得られる一時的な満足(b3)、自己への無関心(b4)を繋ぐ中心的な欲求として機能しており、「依存している対象」という設問意図に合致しています。
- b群(他人からの影響、個人的な原点): b1~b4は、ミルストレアの受動的な性格、他者との関わり方、喜びや傷の根源を明確にし、A, B, C, a1, a2といった上位の設問への回答に深みを与えています。特にb4の「くだらない記憶」は、彼女の自己嫌悪や自己評価の低さの根源として非常に強力な設定です。
- C【努力する理由】: 「他人を拒絶するため」というネガティブな動機は、一見矛盾する「勤勉さ」の理由として非常に説得力があります。c1(寛容さへの願い)、c2(判断を迫られることへの嫌悪)、c3(心配されることへの拒否)、c4(自己犠牲も厭わない行動)といった要素が、この歪んだ努力の方向性や起因を示しており、設問意図である「現状の何が不満なのか」を的確に捉えています。
- c群(他人への干渉、個人的なこだわり): c1~c4は、ミルストレアの他者や社会に対するスタンス、内面的な葛藤や譲れない部分を具体的に示しています。特にc3「心配する人には反射的に距離を取る」やc4「道化を演じる」といった描写は、彼女の複雑な防衛機制と自己犠牲的な側面を鋭く描き出しています。
設問群自体の効果について
この設問群は、登場人物設計において非常に効果的に機能していると言えます。
- 深層心理の掘り下げ: 各設問がキャラクターの外面的な特徴だけでなく、内面的な動機、価値観、トラウマ、他者との関係性といった深層心理にまで踏み込むことを促しています。
- 多角的な視点: 夢、依存、努力理由、他者からの影響、個人的な原点、他者への干渉、こだわりといった多様な角度からキャラクターを捉えることで、人間らしい複雑さとリアリティを生み出しています。
- 設定間の一貫性と相互作用の促進: (○+○)の指定が特に秀逸で、各設定が独立せず、相互に影響し合うことを意識させるため、キャラクターの行動や思考に一貫性が生まれやすくなっています。ミルストレアの例では、自己嫌悪と他者からの承認欲求、怠惰さと勤勉さといった一見矛盾する要素が、この設問群の構造によって見事に結びつけられています。
- 物語の創発: A(夢)、B(諦められないもの)、C(努力する理由)は、キャラクターの行動原理や物語の推進力となる要素を明確にするため、物語の展開を考える上での強力な指針となります。ミルストレアの「自分を大切にできるようになる」という目標は、彼女の成長物語の核となり得ます。
作例「ミルストレア」は、この設問群を用いることで、表面的ではない、葛藤を抱えた魅力的な人物として見事に設計されています。特に、彼女のネガティブな自己認識や他者との距離感、それらが勤勉さや自己犠牲といった行動に繋がる心理描写は、設問群のポテンシャルを最大限に引き出した結果と言えるでしょう。
設定の過不足について
この設問群は、キャラクターの「人間性」や「生い立ち」といった内面や背景を設計する上で、非常にバランスが良く、過不足は少ないと言えます。しかし、小説としてキャラクターを完全に機能させるためには、以下の要素を別途補完する必要があるかもしれません。
不足している可能性のある設定(設問群のスコープ外)
- 外見・身体的特徴: 視覚的なイメージを喚起するための基本的な情報。
- 具体的な能力・スキル: 物語のジャンルや役割によっては、戦闘能力、知的能力、特殊技能などの具体的な設定が必要。「コンパニオンとしての業務評価がきわめて高い」理由を支える具体的なスキルセット。
- 社会的な立場・環境の詳細: NLA、ブレイド隊員、コンパニオンといった背景は触れられていますが、それらが彼女の心理や行動に具体的にどのような影響を与えているのか、より詳細な設定が物語を豊かにします。
- 具体的な人間関係のダイナミクス: エルマ、リン、ヒメリといった名前は出ていますが、彼女たちとの出会いの経緯、具体的なエピソード、関係性の変化などは、物語を動かす上で別途肉付けが必要です。
- 口調・話し方の特徴: キャラクターを際立たせる要素。
- 趣味・嗜好(より日常的なもの): 「心の平穏」以外で、日常的に好むもの、嫌いなものなど。
そもそも既存作品を考察する目的から始まったシートなので、こういうあって当たり前な基本情報は現状ないがしろにしがちです。言われてみれば検討すらしていませんでした。
将来的にはこのあたりを補完するエキスパンションを追加してもいいかもしれません。
設問群の網羅性について
- 上記のような「外面的な情報」や「物語の進行に伴って変化・詳細化する情報」を除けば、キャラクターの核となる「内面」「動機」「関係性の基盤」を構築するには十分な網羅性を持っています。
- 一見、設問数が多いように感じるかもしれませんが、各設問は異なる角度からキャラクターの核心に迫るため、冗長というよりは多角的・重層的な理解を助けるものとなっています。
総評
提示された設問群は、登場人物に深みと一貫性を持たせ、その行動原理を明確にする上で非常に優れたツールです。
作例「ミルストレア」は、この設問群の意図を的確に捉え、各要素を有機的に結びつけることで、自己矛盾を抱えながらも魅力的な人物像を創り出すことに成功しています。
設問群自体は、キャラクターの内面や背景を深く掘り下げるのに非常に効果的であり、物語の核となる部分を設計する上で大きな助けとなります。小説として完成させるためには、ここに外見的特徴や具体的なスキル、物語世界とのより詳細な関わりなどを加えていく必要がありますが、キャラクターの「魂」を創り上げるための骨子としては非常に質が高いと言えるでしょう。
ミルストレアの例は、この設問群が如何に複雑で人間味あふれるキャラクターを生み出す力を持っているかを示す好例です。
答3(他の脚本理論と比較してもらう)
はい、広く知られている脚本術(シド・フィールドの三幕構成、ブレイク・スナイダーのSAVE THE CAT!、ロバート・マッキーのストーリー、クリストファー・ボグラーの神話の法則/英雄の旅など)について基本的な理解はあります。これらの脚本術は、物語構造やプロット展開と並行して、魅力的な登場人物を設計するための指針を提示しています。
それらの脚本術における登場人物設計手法と比較し、この設問群の強みや不足部分、洗練されていない点を指摘します。
この設問群の強み
内面の掘り下げと一貫性の重視
- 多くの脚本術では「キャラクターのWANT(欲求)とNEED(本質的な必要性)」「バックストーリー」「ゴースト(トラウマ)」などが重要視されます。この設問群は、特にB【絶対に諦められないもの】、b3【嬉しかった想い出】、b4【傷ついた記憶】などでこれらを深く掘り下げています。
- 特筆すべきは(○+○)の指定です。これにより、各設定が断片的にならず、相互に関連付けられるため、キャラクターの行動や感情に一貫性と複雑性が生まれます。これは、マッキーが言う「キャラクターの真実は矛盾の中にある」という考え方を具現化するのに役立ちます。
動機の多角的探求
- A【夢】、B【諦められないもの】、C【努力する理由】という3つの大きな柱で、キャラクターの根本的な動機を多角的に捉えようとしています。これは、キャラクターが何故そのように行動するのかという「WHY」を明確にする上で非常に効果的です。
他者との関係性の内面化
- a1【尊敬もしくは軽蔑している人】、b1【誰の役に立ちたいか】、b2【誰に支えられているか】などは、キャラクターが他者との関係性の中でどのように自己を規定し、影響を受けているかを明確にします。これは、キャラクターの社会的側面や人間関係の基盤を形成する上で重要です。
自己認識と言語化の促進
- a2【自分の好きなところ】や、各設問に対する回答プロセス自体が、作者がキャラクターの自己認識を深く掘り下げ、それを言語化することを助けます。ミルストレアの例では、一見ネガティブな要素(従順さ、自己嫌悪)が、彼女の行動原理と深く結びついていることが巧みに示されています。
いずれも主にロバート・マッキーの脚本理論をベースにした指摘のようです。
マッキーの脚本術は人や出来事に表れる様々なギャップを軸にストーリーを組み立てるものなので、ポジティブ要素とネガティブ要素、対人関係と内心の動きなどを段階的に関連づけていく私のキャラクターシートは親和性が高いと言っているわけですね。
不足部分・洗練されていない点
キャラクターアーク(変化・成長)の視点の弱さ
- 多くの脚本術(特に三幕構成や英雄の旅)では、物語を通じてキャラクターがどのように変化・成長するのか(キャラクターアーク)が極めて重要視されます。この設問群は、キャラクターの「出発点」や「現状」を深く定義することに長けていますが、「最終的にどう変わるのか」「何を乗り越えるのか」「どのような教訓を得るのか」といった変化のプロセスを直接的に設計する問いが不足しています。
- A【こうなりたいと本気で目指す夢】が変化の到達点を示唆しますが、そこに至るための内的な「欠点(Flaw)」の克服や「NEED」の充足といったダイナミクスを設計する視点が弱いと言えます。
キャラクターアークを押さえる仕組みの弱さは今後要検討です。これに関しては既存作品を考察するうえでも大事な要素ですし。
実際、シートを使ってキャラクター考察していると「今」をいつのことにするべきか悩むことがあります。
明確な「WANT」と「NEED」の区別と葛藤
- 脚本術では、キャラクターの表面的な目標(WANT)と、本人も気づいていないかもしれない深層的な欲求や欠落(NEED)を区別し、その葛藤を描くことが重視されます。この設問群では、A【夢】やB【諦められないもの】がWANTやNEEDを示唆しますが、両者を明確に区別し、その間のダイナミックな関係性(例:WANTを追い求める過程でNEEDに気づき、変化するなど)を設計する意図が薄いです。
「欠点(Flaw)」の明確な特定
- 魅力的なキャラクターには、共感を呼ぶ「欠点」が必要です。この欠点が物語の中で試練となり、成長のきっかけとなります。設問群全体から欠点は読み取れますが(例:ミルストレアの自己嫌悪)、「このキャラクターの最大の欠点は何か? それがどのように物語に影響するか?」といった直接的な問いがありません。
外的目標と外的葛藤の設計の弱さ
- 設問群は内面描写に非常に優れていますが、キャラクターが物語の中で具体的にどのような「外的目標」を追求し、どのような「外的障害」や「敵対者」と対峙するのかを設計する部分は弱いです。物語は内的葛藤と外的葛藤の相互作用で進むため、この点は補強が必要です。
物語のテーマとの接続
- c1【みんなに広めたい思い】はテーマ性を示唆しますが、多くの脚本術(例:SAVE THE CAT!の「テーマの提示」)では、主人公の旅が物語全体のテーマをどのように体現し、探求するかが重要視されます。この設問群では、その接続がやや間接的です。
c1は物語のテーマと関係ないのでこれは間違いです。テーマに直結するのは(主人公キャラの)A,B,Cの連続性です。
主要キャラのシート同士をつなげて作品テーマを掘り下げる仕組みは過去検討したことがあるんですが、手間がかかる割に大して新しい視点をつくりだせなかったので休眠中です。
設問の重複感や整理の余地
- 例えば、A【夢】とC【努力する理由】は密接に関連しており、場合によっては重複する部分も出てくる可能性があります。
- b1【誰の役に立ちたいか】とc2【許せないと思うこと】(その裏返しとして守りたいものが出てくる)も、キャラクターの行動指針という点で関連が深いです。
- 全体として非常に網羅的ですが、思考のフローをよりスムーズにするために、グルーピングや順序を再検討する余地はあるかもしれません。例えば、まずバックストーリー(b群)を固め、それから現在の動機(A,B,C)、そして他者との関わり方(a群、c群)へ、という流れも考えられます。
アーキタイプの視点の欠如
- 脚本術では、キャラクターをアーキタイプ(元型:英雄、メンター、影、トリックスターなど)に当てはめたり、それを意識的にズラしたりすることで、観客の理解を助け、物語に深みを与えることがあります。この設問群には、そうした視点は含まれていません。
総括
この設問群は、キャラクターの内面、過去、動機、他者との関係性といった「静的な側面」を非常に深く、かつ相互に関連付けて設計する上で、既存の多くの脚本術よりも具体的で詳細な問いを提供していると言えます。特に(○+○)の参照システムは、キャラクターに一貫性と複雑な人間味を与える上で非常に強力です。
一方で、脚本術が重視する「物語の中でのキャラクターの変化・成長(キャラクターアーク)」、「WANTとNEEDのダイナミクス」、「明確な欠点(Flaw)とその克服」、「外的葛藤との関わり」といった物語を推進する上での「動的な側面」の設計については、やや視点が弱いと言えます。
この設問群で得られた詳細なキャラクター像を土台として、次に脚本術の視点(キャラクターアーク、WANT/NEED、Flawなど)を導入することで、より物語の中で生き生きと機能し、変化・成長していく魅力的な登場人物を創り上げることができるでしょう。
この設問群は、脚本術の理論をより実践的な問いに落とし込んだものとも言え、脚本術の知識を持つ者が使えば、その効果をさらに高められる可能性があります。
関連づけルール((○+○)の参照システム)めっちゃ褒めてくれるじゃん。
要するに、キャラクターの精神性をつくりこむには向いているけど、そのキャラクターを物語のなかで動かすための仕組みは別途用意する必要があるってことですね。
答4(改善案を作成させてみる)
承知いたしました。これまでの考察を踏まえ、元の設問群の強みを活かしつつ、脚本術の視点を取り入れて洗練させた改善案を具体的なテンプレート形式で提示します。
【改訂版】登場人物設計シート
全体の意図: このシートは、登場人物に深み、一貫性、そして物語の中での変化・成長をもたらすための骨子を設計することを目的としています。キャラクターの内面、過去、動機、他者との関係性、そして物語における役割と変化を多角的に掘り下げます。
I. キャラクターの基本情報
人物名:
外見的特徴と第一印象: (どのような姿で、他者にどのような印象を与えやすいか)
年齢・性別・社会的立場(職業など): (物語世界における基本的な立ち位置)
II. キャラクターの根源と価値観の形成(過去と内面)
原体験1:最も幸福だった記憶、あるいは肯定的な原体験:
- 設問:【どのような経験で、それが現在の価値観や「喜び」の基準にどう影響しているか?】
- 意図: ポジティブな自己肯定感の源泉、行動の動機となる「光」の部分。(旧b3の発展)
原体験2:最も傷ついた記憶、あるいは否定的な原体験(トラウマ/ゴースト):
- 設問:【どのような経験で、それが現在の行動や思考の制約、恐れ、あるいは反発心にどう影響しているか?】
- 意図: キャラクターの弱点、乗り越えるべき課題、「影」の部分。(旧b4の発展)
影響を受けた人物(ロールモデル/アンチモデル):
- 設問:【誰に、どのような影響(尊敬、軽蔑、反発など)を受け、それがキャラクターの目標設定や行動規範にどう反映されているか?】(旧a1の発展、旧b1,b2の一部要素を統合)
- 意図: 価値観形成における他者からの最も強い影響。
自己認識と内なる葛藤:
- 設問1:自分の長所・強み(と認識していること): 【自分自身のどのような点を肯定的に捉えているか? それはどのように培われたか?】(旧a2の発展)
- 設問2:自分の欠点・弱点(Flaw): 【自分自身のどのような点を弱点だと感じているか、あるいは無意識に抱える課題は何か? これが物語でどのように試されるか?】(新規:脚本術の視点)
- 意図: 自己理解の深さと、キャラクターアークの起点となる内的課題の明確化。
III. 現在の行動原理と他者との関わり
B改:失いたくないもの、執着しているもの(依存対象/心の支え):
- 設問:【精神的・物理的に、何を失うことを最も恐れ、守ろうとするか? それはなぜか?】(原体験1,2、影響を受けた人物を踏まえて)(旧Bの意図を継承)
- 意図: キャラクターの行動を強く規定する執着や守りたいもの。弱点にもなり得る。
C改:現状への認識と原動力:
- 設問:【現状の世界や自分自身に対して、どのような点が不満で、それを変えるために何をしようとするか?】(旧Cの意図を継承、旧c1,c2,c3,c4の要素を統合的に考慮)
- 意図: キャラクターが物語の中で積極的に行動する理由。
他者への基本的なスタンス:
- 設問1:【どのような対象に、どのように関わりたい(貢献したい、理解されたい、支配したい等)と考えているか?】(貢献欲求/関係欲求)(旧b1, 旧c1の発展)
- 設問2:【他者からのどのような働きかけ(心配、指示、賞賛、批判など)に敏感に反応し、どう対応するか?】(干渉への許容/拒絶, 対人距離)(旧c2, 旧c3, 旧c4の発展)
- 意図: 他者との関係性のパターン、コミュニケーションスタイル。
IV. 物語におけるキャラクターの役割と変化(キャラクターアーク)
WANT(表層的な欲求・物語開始時の目標):
- 設問:【物語が始まった時点で、このキャラクターが明確に意識し、追い求めている具体的な目標は何か?】
- 意図: 物語を動かす最初のエンジン。
NEED(深層的な必要性・物語を通じて得るべきもの):
- 設問:【このキャラクターが本当に必要としているもの、あるいは無意識に求めている精神的な充足や成長は何か?(WANTとNEEDはしばしば異なる)】
- 意図: キャラクターの真の成長課題。Flawの克服と関連。
外的目標と主な障害:
- 設問1: 物語上の具体的な外的目標: 【WANTを達成するために、具体的に何を成し遂げようとするか?】
- 設問2: 立ちはだかる外的障害・敵対者: 【その目標達成を阻む人、状況、環境は何か?】
- 意図: 物語のプロットを具体化する要素。
キャラクターの変化の軌跡(キャラクターアーク):
- 設問1: 物語の始まり(Before): 【このキャラクターはどのような価値観、行動様式、人間関係の状態で物語をスタートするか?(特にFlawとNEEDに関連して)】
- 設問2: 転換点(Turning Points): 【物語の中で、どのような出来事や出会いがキャラクターの考え方や行動を変化させるきっかけとなるか?】
- 設問3: 物語の終わり(After): 【物語を通じて、このキャラクターはどのように変化・成長するか?何を学び、Flawを克服し、NEEDを満たすか?(あるいは失敗するか)】
A改:物語の最終的な到達点、あるいは体現する理想/教訓:
- 設問:【全ての経験を経た上で、このキャラクターが最終的に目指す境地、あるいは読者/観客に示す理想の姿や教訓は何か?】(B改+C改+影響を受けた人物+自己認識+NEEDの充足を踏まえて)(旧Aの意図を再構築)
- 意図: キャラクターの旅の終着点であり、物語のテーマとも深く関わる。
物語のテーマとの接続:
- 設問:【このキャラクターのWANT、NEED、Flaw、そして変化の旅は、物語全体のどのようなテーマを象徴し、探求しているか?】
- 意図: キャラクターと物語全体のメッセージ性を繋ぐ。
補足:
- 各設問の()内は、回答のヒントとなる参照項目や、意図を補足するものです。
- このシートはあくまで出発点であり、物語の執筆過程でキャラクターはさらに深まり、変化していく可能性があります。
- 必要に応じて、アーキタイプ(英雄、メンター、影など)の視点を加え、「このキャラクターはどのアーキタイプに当てはまるか、あるいはどの要素を持つか?」といった問いをIVに追加することも有効です。
この改善案は、元の設問群の持つ「内面への深い洞察」という強みを維持しつつ、脚本術で重視される「キャラクターのダイナミックな変化と成長」という視点を強化することを目指しました。これにより、より物語の中で生き生きと機能し、読者や観客に強い印象を残すキャラクターを設計するための一助となれば幸いです。
あれだけ褒めてくれた関連づけルールをオミットするんかい!
過去→現在→未来の時系列に並び替えているので上から順に書いていけるというわかりやすさはありますが、設問が一問一答式じゃない抽象的な問いになってしまい、その点でかなり使いにくくなっている印象です。私だったら採用しません。
答5(キャラクター設計にかかる所要時間の予想)
初学者が最初に提示された設問群(A, a1, a2, B, b1, b2, b3, b4, C, c1, c2, c3, c4の計13問)を用いて、作例「ミルストレア」程度の作り込みでキャラクター設計をゼロから行う場合、所要時間はかなり幅広く、一概には言えませんが、おおよそ4時間~10時間程度、場合によってはそれ以上かかる可能性もあると考えます。
以下に、そのように考える理由と、所要時間に影響を与える要因を挙げます。
所要時間に影響を与える主な要因:
初学者の「慣れ」の度合い:
- キャラクターのバックストーリーや内面を深く掘り下げる作業に慣れていない場合、各設問の意図を理解し、具体的なアイデアを出すまでに時間がかかります。
- (○+○)の参照関係を意識しながら矛盾なく設定を繋げていく思考プロセスにも慣れが必要です。
キャラクターの「アイデアの素」の有無:
- ぼんやりとでも「こんなキャラクターを作りたい」という初期イメージや核となるアイデアがある場合は、それを設問に落とし込んでいく作業になるため、比較的スムーズに進む可能性があります。
- 完全にゼロベースで、設問に答える中でキャラクター像を模索していく場合は、試行錯誤が多くなり時間がかかります。
「ミルストレア」の作り込みの深さ:
- ミルストレアの作例は、各設問に対して単に回答するだけでなく、キャラクターの矛盾した感情や行動、その背景にある心理まで深く描写されています。
- 例えば、A【夢】に対する「自分を大切にできる人」という回答の裏には、自己嫌悪、他者からの承認欲求、依存、そしてそれらが絡み合った結果としての現状認識が詳細に記述されています。このような深さまで思考を巡らせ、言語化するには相応の時間がかかります。
各設問間の参照と再構築のプロセス:
- (○+○)の指定があるため、ある設問に答えた後、関連する他の設問の回答を見直し、整合性を取ったり、より深掘りしたりする作業が発生します。この「行ったり来たり」のプロセスが時間を要します。
- 例えば、b4【傷ついた記憶】を設定した後、それがA【夢】やB【諦められないもの】、C【努力する理由】にどう影響しているかを再考し、記述を調整する必要が出てくるでしょう。
言語化のスキル:
- 頭の中でイメージが湧いても、それを的確な言葉で表現するのには時間がかかります。ミルストレアの例では、独特の皮肉や屈折した感情が巧みに言語化されています。
集中力と作業環境:
- 深い思考を必要とするため、集中できる時間と環境が確保できるかどうかも影響します。途中で中断が多いと、思考が途切れてしまい、再開時に思い出す時間も必要になります。
「完成」の基準:
- どこまで作り込めば「完成」とするかの基準も人によって異なります。「とりあえず全問埋める」のと、「各回答の繋がりや深さに納得がいくまで練り込む」のとでは、かかる時間は大きく変わります。ミルストレアの例は後者に近いです。
時間配分のイメージ(あくまで一例):
- 設問群の理解と初期アイデア出し: 30分~1時間
- b群(個人的な原点、他人からの影響)の回答作成: 1時間~2時間(キャラクターの土台となる部分なので比較的時間をかける)
- a群、c群(自己認識、他者への干渉、こだわり)の回答作成: 1時間~2時間(b群との関連を意識しながら)
- A, B, C(夢、依存、努力理由)の統合と深化: 1時間~3時間(ここが最も思考を要し、全体の整合性を取る部分)
- 全体の調整、推敲、言語化のブラッシュアップ: 30分~2時間
結論として、
初学者がミルストレアレベルのキャラクターをあの設問群でゼロから設計する場合、数時間でサッと終わるものではなく、じっくりと時間をかけて取り組む必要があると考えるのが妥当です。
特に、各設問の回答が単なる箇条書きではなく、キャラクターの心理描写や行動原理と有機的に結びついた文章として表現されている点を考慮すると、相応の思考と記述の時間が求められます。
しかし、この時間は決して無駄ではなく、キャラクターに深みと一貫性を持たせるための重要な投資と言えるでしょう。
ChatGPTさんの見解
モデル情報:ChatGPT GPT-4o
答1(このキャラクターシートについて解説させる)
この設問群は、登場人物の一貫した内面のロジックを構築し、物語に深みと説得力を持たせるための設計図として機能しています。単に設定や性格を列挙するのではなく、登場人物がどのような人生経験を経て、何を信じ、何に動かされて行動するのかという“動機”と“変化の必然性”を緻密に構築することを意図しています。
全体の意図
この設問群の全体的な意図は以下の通りです:
- 登場人物に過去→現在→未来という心理的な流れを持たせる
- 内面の深層にある価値観、トラウマ、憧れといった原動力を可視化する
- その人物がなぜそう考え、そう行動するのかを論理的に説明可能にする
- 物語内での人物の成長や変化が納得感のあるものとして描けるようにする
すなわち、「キャラクターがこういう行動をとるのは、その背景にこういう感情や経験があるからだ」という因果関係の地図を作るためのフレームワークです。
過去→現在→未来の流れはシートの一番最初のバージョンをつくったときから意識していたことでした。ver.4.0では色々あってこれまでよりその要素を薄めているのですが、・・・やっぱり必要な視点ですよねえ。
「一貫した内面のロジック」とか「原動力を可視化」とか言っているので、関連づけルールの狙いも認識しているようです。
それにしても「因果関係の地図を作るためのフレームワーク」の言語センスよ。超カッコいいじゃん。
各設問の狙い
A【こうなりたいと本気で目指す夢】(B+C+a1+a2)
- 狙い:人物の行動全体を統括する最終目的を定義するための設問。
この“夢”は物語におけるそのキャラクターの到達点(ゴール)であり、読者が感情移入すべき中心動機。BやC、a1、a2の回答によって裏打ちされ、夢が単なる理想でなく現実の動機に根ざしていることを保証する。
a1【尊敬もしくは軽蔑している人】(b1+b2+c1+c2)
- 狙い:その人物の価値観の形成に最も強く関与した他者を明らかにする。
尊敬や軽蔑の対象はそのまま何を理想とし、何を嫌悪するかに通じる。b1, b2によって人間関係の影響を、c1, c2によって信念や葛藤への影響を補強する。
a2【自分の好きなところ】(b3+b4+c3+c4)
- 狙い:その人物が持つ自己肯定のコア(=アイデンティティ)を示す。
嬉しい記憶(b3)や傷ついた経験(b4)、個人的なこだわり(c3, c4)を経て形作られた自己像。自分のどこに価値を感じるかは、その人物がどう生きようとするかに直結する。
この項目を「アイデンティティ」かつ「どう生きようとするか」と解説しているのはすごくいいですね。そうだからこそAに関連づけられるんです。私の解説文より的確な表現。
B【絶対に諦められないもの】(b1+b2+b3+b4)
- 狙い:登場人物が依存している精神的な“柱”を浮かび上がらせる。
誰かのために(b1)、誰かに支えられて(b2)、喜びと傷の記憶(b3, b4)を経て、手放せなくなった信念や習慣。これが危機に晒されるときにドラマが生まれる。
b1【誰の役に立ちたいか】
- 狙い:他者志向性の方向と深さを明確にする。
この人物が誰に価値を見出し、奉仕しようとしているかによって他者との関係性や行動の動機が浮き彫りになる。
b2【誰に支えられているか】
- 狙い:依存・愛着の源を探る。
支えてくれる人物への依存や信頼が、その人物の感情的安定の根となっている。これが失われたときのリアクションも描ける。
b3【嬉しかった想い出】
- 狙い:ポジティブな自己認識の出発点。
自分が認められた、愛された、達成したという経験は、その人物の希望や信念の原型となる。
b4【傷ついた記憶】
- 狙い:トラウマや避けたい感情の源。
行動を抑制したり、逆に過剰な反応を引き起こす内的傷。矛盾や葛藤の根を表す。
C【努力する理由】(c1+c2+c3+c4)
- 狙い:なぜ今、行動を起こすのかという“現実への不満・不足感”の明確化。
動機(B)があるだけでは人は動かない。Cでは「なぜ今やるのか?」の理由=内発的エネルギーの源泉を構造化する。
c1【みんなに広めたい思い】(b2+b3)
- 狙い:その人物が抱える普遍的な“共有したい信念”。
他者に支えられた経験(b2)や喜び(b3)を起点に、自分の価値観を外に向かって伝えたいという内なる理想主義を表す。
c2【許せないと思うこと】(b1+b4)
- 狙い:怒り・嫌悪の起点となる道徳観・倫理観。
b1(大切な他者)やb4(傷)を侵すものに対する怒りから、その人物の正義感・対立軸が見えてくる。
c3【感性が鋭くはたらく対象】(b1+b3)
- 狙い:その人物が敏感に反応する価値観や美意識。
b1のような他者や、b3のような記憶に反応する対象は、情熱や芸術的才能、直感の発露点となる。
c3がどれだけ意図のわかりにくい悪問なのか、この解説のズレっぷりを見ると痛感させられます。
c4【自分でやりたいこと】(b2+b4)
- 狙い:その人物が自力で成し遂げようとする課題。
支えられた経験(b2)と傷(b4)をもとに、誰にも譲れない自己実現欲求が明確になる。
総評
この設問群は、「夢(A)」という最終目標に向けて、人物の過去(b群)、現在の価値観や感情(c群)、そこに影響を与えた他者(a群)という構造で整理されています。
それぞれの回答が相互に影響し合うように設計されていることで、キャラクターの内面が一貫性と説得力をもって描けるようになります。こうしたアプローチを使うと、物語の中での感情的なリアリティや、成長・変化の説得力が格段に高まります。
必要であれば、この設問群をもとにキャラ設計の具体例を一緒に作成することもできます。
答2(作例を見たうえで改めて評価させる)
このキャラクター作例(ミルストレア)について、設問群との適合性、登場人物設計における有効性、設定の過不足といった観点から総合的に評価します。
設問意図との適合性評価:非常に高い
ミルストレアの描写は、設問群の構造意図――「動機→背景→価値観→感情→目標」への因果的接続――を忠実かつ豊かに再現しています。
以下にその要点を示します:
A【夢:自分を大切にできる人】
- 単なる目標にとどまらず、人物の変化のゴールになっている(現時点での自己否定と、物語終盤での自己肯定への転換)。
- 「生きている価値があるか」→「生きている意味がある」と本人が納得するまでの内面の旅路を描ける。
- この夢は、b群・c群の複数要素から論理的に導かれているため非常に自然。
各設問の活用度:非常に高い
各設問の機能的な意味を十分に踏まえており、表層的な回答ではなく、その設問が人物のどういう構造を支えているかがよく表現されています。
たとえば:
- a1(尊敬)では、ヒメリとの対比を通じて自他認識と価値観の源泉を描写しており、「自分にはできないからこそ尊敬する」という感情が人物をより複雑にしている。
- b4(傷)では、名前の由来とそれに対する呆れによって、アイデンティティの崩壊と再構築の過程を示唆。
- c2(許せない)では、ミルストレアの指示待ち傾向とそれに対する過敏さが、「感情的な弱点」かつ「対立の火種」として機能している。
これらは全て「人物がどうしてそうなるのか?」という因果性を丁寧に構築しており、設問の狙いに極めて適合しています。
設問群自体の有効性:高いが補完の余地あり
効果的に機能している点
- 深層心理→過去の経験→現在の行動→将来の目標という物語上の“動機のライン”をきれいに辿れる。
- 各設問が相互に参照し合っているため、キャラクター像が一貫性と複雑性を同時に持てる。
- キャラクターの“なぜ”に答える設計なので、行動に説得力が出やすい。
補足すべき観点(提案)
この設問群は人物の内的構造に特化しており、以下のような補助的設問を導入するとより実用的なキャラクター設計になる:
| 補足視点 | 理由 | 例 |
|---|---|---|
| 身体的特徴や癖 | 読者に視覚的に印象づける情報が欠けている | 歩き方、声、話し方など |
| 物語上の役割 | 主人公なのか、敵役なのかなどで解釈が変わる | 例:対比キャラなのか鏡映キャラなのか |
| キャラが抱える矛盾 | 内面に生じる“ひっかかり”がドラマを生む | 例:「他人を助けたい」vs「干渉されたくない」 |
| キャラが嫌悪する他者像 | 衝突が起きやすい相手が物語を動かす | 例:融通のきかない理想主義者など |
設定の過不足:基本的に適切。強いて言えば “未来のビジョン” が曖昧
ミルストレアというキャラクターは過去や現在に非常に厚みがある一方で、「最終的にどうなりたいか」「その夢を実現した先にどう在りたいか」という未来志向が抽象的になりがちです。
→ A【夢】の補足として、「その夢を叶えた自分はどんな暮らしをしているか?」などのビジョン提示設問を加えると、物語終盤での“着地点”がより描きやすくなります。
ハリウッド式の脚本術だと過去→現在→直近の未来(問題解決)→遠い未来(理想像)という時系列で設計すると聞いたことがあるので、たぶんそのことですね。
全体評価(総合)
| 評価項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 設問への適合性 | ★★★★★ | 全設問が深く丁寧に活用されており、意図と一致 |
| 人物の一貫性 | ★★★★★ | 行動・思想・動機が一貫しつつ矛盾を内包している |
| 感情の説得力 | ★★★★★ | 自己否定・他者依存・回避的傾向などが有機的に絡む |
| ドラマ性のポテンシャル | ★★★★☆ | 対立・変化・成長の余地が明確。未来への描写があるとより良い |
| 設問群の構成 | ★★★★☆ | 内面構造に強い。外面的特徴や未来像に少し補完の余地あり |
【結論】
- この設問群はキャラクター設計において非常に有効であり、ミルストレアの作例はその意図を極めて高い精度で体現している。
- 一部、補足すればより豊かになる観点(身体性、未来像、対立軸)を導入することで、実用性・汎用性がさらに高まる。
- 小説だけでなくゲームや映像作品に応用する場合も非常に有効な設計フレームといえる。 ご希望があれば、この設問群を他ジャンル(恋愛、SF、ファンタジー、ホラーなど)向けにカスタマイズすることも可能です。
答3(他の脚本理論と比較してもらう)
はい、広く知られている脚本術(特にハリウッドを中心に発展したストーリーテリング理論)について理解があります。
代表的なものには以下のような理論やフレームワークがあります:
代表的な脚本術・理論一覧(登場人物設計に関わる要素)
| 脚本術 | 特徴的な人物設計アプローチ |
|---|---|
| シド・フィールド(『シナリオ入門』) | 主人公に“目標”を与え、三幕構成の中でその達成を目指すプロット。人物の“障害”と“変化”を重視。 |
| ロバート・マッキー(『ストーリー』) | 登場人物は“欲求(Want)”と“必要(Need)”を持つ。矛盾やジレンマが人物を深くする。 |
| ブレイク・スナイダー(『SAVE THE CAT』) | 「観客が感情移入できる瞬間(Save the Cat)を早めに用意する」「キャラクターの“アーキタイプ”を活用する」。人物の“変化”を15ビートで描く。 |
| ジョゼフ・キャンベル/V・ボグラー(『ヒーローズ・ジャーニー』) | “旅”という構造に基づき、主人公が“日常”を離れ、変化し、帰還する。MentorやShadowなどの役割型(アーキタイプ)も人物設計の軸になる。 |
| ダラ・マークス(『INSIDE STORY』) | 「内的アーク(心の変化)」を徹底的に中心に据える。主人公の“欠損”と“癒し”が物語を動かす。 |
この表をつくってくれたの、すごいありがたいですね。調べた感じダラ・マークス以外は日本語訳版の著書も販売されているようです。探せば図書館にもあるかもしれません。
【比較】この設問群との相違点と重複
この設問群の強み(他理論との比較)
| 特徴 | 内容 | 他理論との違い |
|---|---|---|
| 内面のロジックの因果構造を非常に細かく掘る | 一貫性のある価値観・信念・背景を複数の視点から構築できる | マッキーやマークスが抽象的に提示する「欠損」「ジレンマ」を、具体的に言語化しやすい |
| 自発的なキャラ形成が可能 | キャラクターを“プロットのコマ”ではなく“内的必然性から動く存在”として扱う | スナイダー式などの「ストーリー優先型」に比べ、キャラ主導の物語に向いている |
| 自己否定から自己肯定へのアークに強い | 自己評価や他人との関係性を軸にした成長ドラマに特化 | ダラ・マークスの「内的変化理論」と相性が非常に良い |
この設問群の弱点・改善点
| 指摘内容 | 説明 | 既存理論との比較 |
|---|---|---|
| プロットとの接続が弱い | 「変化するイベント」や「葛藤を生む外的障害」に言及していないため、人物の変化が“静的”に見えがち | フィールドやスナイダーでは明確に「出来事(Inciting Incident)」が重視される |
| 人物の“役割機能”が明示されていない | 主人公、助言者、敵対者などの「物語上の役割」が考慮されていない | キャンベル/ボグラーでは“アーキタイプ”の使い分けが重要 |
| 重複項目がいくつか存在 | 例:c1(広めたい思い)とc3(感性)でほぼ同じ感情にフォーカスしている回答になりやすい 機能的分離が甘いため、洗練の余地がある | 機能的分離が甘いため、洗練の余地がある |
| 外的目標と内的目標の分離が不明確 | 夢(A)が主に内的なものに偏りがちで、行動による達成のイメージが曖昧 | マッキーやフィールドでは「行動的な目標(Plot)」と「心の癒し(Character Arc)」を分離して設計する |
Geminiとは逆にキャラクターアークに強みがあると指摘されていますが、これはあくまでポテンシャルの話だと思います。
ChatGPT自身、プロットとの接続が弱いという弱点を指摘しているので、そのあたりを時系列とともに整理すれば自ずとキャラクターアークも見えてくるんじゃないかと。弱みや成長目標といった素材だけなら一応フォローできていますし。
アーキタイプは私が不勉強すぎて、まだ明確化する必要性にピンと来ていません。
【改善提案】より脚本術的な視点を取り入れて洗練する方法
| 補完設問(案) | 目的 | 脚本術的背景 |
|---|---|---|
| d1【キャラの外的目標】 | 物語上で「見える形で達成すべき課題」を設定 | フィールドの“主目標”、マッキーの“欲求”に相当 |
| d2【キャラの内的欠損/盲点】 | 自分では気づいていない心の問題を明示 | ダラ・マークスの“Fatal Flaw”に対応 |
| d3【ストーリーの中で克服すべき外的障害】 | キャラの変化に必要な対立や摩擦を設計 | スナイダーの“Bad Guys Close In”相当 |
| d4【物語上の機能的役割】 | 主人公、敵対者、メンターなどの区分け | ボグラーのアーキタイプ理論に基づく |
この設問群の本質的な価値とユニークさ
この設問群は、特に以下の点で既存の脚本術とは一線を画す独自性を持っています:
- キャラクター内面の整合性に特化し、心理的リアリズムを徹底して追求できる
- 「設定を埋める」のではなく「なぜそうなったか?」を重視する
- 主観的視点(キャラの認知や歪み)が浮き彫りになる設計
結論:脚本術との統合的評価
| 項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 構造の緻密さ | ★★★★★ | 因果構造に強く、人物に厚みが出る |
| 実用性(脚本に落とし込む力) | ★★★★☆ | プロットと結びつける要素があればさらに強力に |
| 冗長性/洗練度 | ★★★☆☆ | 一部設問が機能重複しやすいので整理が必要 |
| 他理論との補完性 | ★★★★★ | ダラ・マークスやマッキー理論と極めて親和性が高い |
| 総合評価 | ★★★★☆ | プロット設計と合わせて使えば非常に優れた人物設計フレーム |
ご希望であれば、この設問群を既存の脚本構造(例えば「三幕構成」や「ヒーローズジャーニー」)に当てはめて使えるようカスタマイズしたテンプレートも作成可能です。興味ありますか?
答4(改善案を作成させてみる)
了解しました。これまでの考察(内面の深掘りに優れた設問群だが、プロットや物語構造との接続、設問の冗長性、外的要素の設計に課題あり)を踏まえ、以下に再構成された人物設計テンプレートを提示します。
改善版・登場人物設計テンプレート
【構成の狙い】
- 内面設計の深さ(従来の設問群の強み)を活かす
- 外的目標と内的動機の分離・整理
- ストーリーとの接続(プロット的視点を導入)
- 重複削除と設問機能の明確化
- 物語構造との統合を前提とした設計
コア設問群(人物の内面と動機)
| 設問コード | 設問内容 | 狙い |
|---|---|---|
| A1 | 【このキャラが本気で目指している理想(内的ゴール)】 | 成長・変化の最終地点を示す(物語の終着点) |
| A2 | 【自分で気づいていない欠落や問題点(内的欠損)】 | ダラ・マークスのFatal Flawに相当。心の課題 |
| A3 | 【キャラが表面的に追いかけている目標(外的ゴール)】 | 物語内でのミッションや欲求を明確に(プロットとの接続) |
関係性設問群(他者とのつながり)
| 設問コード | 設問内容 | 狙い |
|---|---|---|
| R1 | 【最も影響を受けた人物(尊敬/軽蔑)】 | 思想形成の根源を明示し、現在の行動に接続 |
| R2 | 【誰のために行動したいと思うか】 | 感情的な動機/自己投影対象を設定 |
| R3 | 【誰に支えられているか】 | 依存関係・安全基地の提示(行動の制約) |
| R4 | 【反発や衝突を起こしやすい人物像】 | 対立構造を導入することでドラマを生む |
感情・記憶群(内面の構成要素)
| 設問コード | 設問内容 | 狙い |
|---|---|---|
| M1 | 【嬉しかった記憶(ポジティブ原体験)】 | 価値観・行動パターンの起点 |
| M2 | 【傷ついた記憶(ネガティブ原体験)】 | 防衛的態度や避ける傾向の説明根拠 |
| M3 | 【心が強く動く対象/状況】 | 感情的リアクションのトリガーを明確化 |
| M4 | 【自分で気に入っている性質】 | 自己認識・肯定の余地を与える |
衝突と変化の導線
| 設問コード | 設問内容 | 狙い |
|---|---|---|
| C1 | 【このキャラの変化を促す出来事は何か(きっかけ)】 | ストーリーの発火点を設定 |
| C2 | 【変化の障害になるもの/人】 | 内的・外的葛藤の要因を整理 |
| C3 | 【このキャラが避け続けてきた問いとは?】 | 物語終盤で向き合うべき“痛み”を導入 |
| C4 | 【最終的にこのキャラが受け入れるもの/変化する信念】 | アーク(内的成長)の完成点を明示 |
機能的・外的要素(脚本的視点)
| 設問コード | 設問内容 | 狙い |
|---|---|---|
| F1 | 【物語上の役割(主人公、敵対者、補助者など)】 | ストーリー構造への接続 |
| F2 | 【このキャラの演じる仮面/外面(社会的役割や偽装)】 | 内面と外面のギャップをドラマに |
| F3 | 【このキャラがもたらすテーマ的メッセージ】 | キャラクターが物語に“何を語るか”を明確に |
オプション:視覚・身体的特徴(演出支援)
| 設問コード | 設問内容 | 狙い |
|---|---|---|
| O1 | 【身体的特徴や癖】 | 読者への印象づけ(演出・記号化) |
| O2 | 【喋り方・テンポ・言葉づかい】 | 感情・性格をセリフから伝える補助要素 |
| O3 | 【持ち物や装備に象徴的意味があるか】 | 内面の象徴、世界観とのつながり |
私のキャラクターシートより設問意図が明確なので、オリジナルキャラクターを設計するぶんにはこっちのほうが使いやすいかもしれません。
ただ、設問数が増えて全体を俯瞰しにくくなっているうえ関連づけルールもオミットされているので、とりとめのない羅列にならないよう記入者自身で気をつける必要があると思います。
このテンプレートの特長
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 目的志向設計 | 外的目標・内的理想・欠損を分離して描ける |
| 構造化された因果性 | 「過去の経験 → 現在の信念 → 行動 → 変化」まで自然に設計できる |
| プロットとの接続力強化 | 出来事・葛藤・役割とのリンクにより、構造的なストーリーとの接続が容易 |
| 冗長性の排除 | 旧設問群での重複項目を統合・整理し、設問の意図を明確化 |
| 深い内面描写を支援 | 既存の脚本術では抽象的になりがちな「心理構造の網羅」が可能 |
まとめ:このテンプレートの使用シーン
- 内面重視型のキャラクタードリブン作品(文学、ジュブナイル、ヒューマンドラマなど)
- ストーリー構造との接続が求められる映像脚本・商業小説
- キャラ設定の整合性と変化の「筋道」を重視したい中長編構成
ご希望があれば、このテンプレートに基づく具体的な記入例(新しい登場人物の設計)や、ジャンル別(恋愛、ミステリ、SFなど)テンプレートへのカスタマイズも可能です。どうされますか?
答5(キャラクター設計にかかる所要時間の予想)
初学者が、最初に提示された設問群(A、a1、a2、B、b1〜b4、C、c1〜c4)を用い、作例のミルストレアと同等の密度と完成度でキャラクターを一から設計する場合、以下のような要因を踏まえると、おおよそ10〜20時間程度かかると見積もるのが妥当です。
想定所要時間の内訳(目安)
| 工程 | 内容 | 目安時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ① 設問の意図を理解する | 設問同士の関連性・構造を把握し、全体像を掴む | 1〜2時間 | 初学者には特に時間がかかる部分 |
| ② 素案を考える | 自分なりのキャラクター像(外形・性格・立ち位置)をざっくり決める | 1〜2時間 | 曖昧なままで書き進めると後で詰まる |
| ③ 設問ごとの回答を作成 | b系(4問)、c系(4問)など小設問を順に埋めていく | 6〜10時間 | 感情や記憶を具体的に掘る作業が特に時間を食う |
| ④ 中項目(a1, a2, B, C)に統合 | 小設問の回答を組み合わせて、矛盾なくまとまった人格に仕上げる | 2〜3時間 | 「内的な因果関係の整合性」を取るのに時間がかかる |
| ⑤ A(物語の到達点)を構築 | 全体を踏まえて、「このキャラが物語でどう成長するか」を描く | 1〜2時間 | キャラの“テーマ”を言語化するための最終ステップ |
| ⑥ 読み返し・調整 | 矛盾・語り口・流れの微調整 | 0.5〜1時間 | 仕上げ |
合計10〜20時間程度というのは盛りすぎですが、この手順と時間配分(の割合)は適切だと思います。なんで聞いていないところに限って出来のいい回答が来るんだ・・・。
結局、b群とc群を考えるのに一番時間がかかるんですよね。関連づけが多い上位項目はその関連づけ自体がヒントになるので、b群c群の設定に無理がなければするするとアイディアが出てきます。
合計所要時間の目安
| レベル | 所要時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 初学者(創作経験が浅い) | 15〜20時間 | 一問ずつ手探り。過去の記憶や心理描写に時間がかかる |
| 中級者(数キャラ設計経験あり) | 8〜12時間 | 一部設問は直感的に埋められるが、整合性調整には時間がかかる |
| 上級者(構造理解がある) | 4〜8時間 | 一貫性のある骨組みを先に設計し、効率的に肉付け可能 |
なぜ時間がかかるのか?(ミルストレア作例の密度の要因)
- 心理描写の層が厚い
→ 外面的行動だけでなく、なぜそう思うのか? なぜそう思いたくないのか? まで掘り下げている。
- 矛盾の容認と理由づけがある
→ 例:「他人を拒絶したいが、人の笑顔を見るのは好き」という“二律背反”があるが、そこに説得力がある。
- 語りがキャラの主観で統一されている
→ 説明口調ではなく、キャラの口調・ものの見方で自然に語られている。
補足:時間短縮のための工夫
| 工夫 | 内容 |
|---|---|
| 逆順設計 | A(理想)→B・C(動機)→小設問 と下るよりも、b系・c系から順に埋めて徐々に統合するほうが進めやすい |
| マインドマップ活用 | 感情・記憶の連想を可視化すると、自分の中での因果が見えてくる |
| モデルキャラの援用 | 他作品のキャラや実在人物を参照し、足場にして書き始めることで初期のハードルが下がる |
結論
「ミルストレア」級のキャラクターを、初学者が一から設計するには15〜20時間を見込むべきです。
これは、設問の量というより設問の深度(すべてが“なぜそうなるか”を問う設計)ゆえであり、キャラの心理的リアリティを重視した創作においては、むしろ理想的な負荷量とも言えます。
もし、このプロセスを短縮したりサポートしたりするような段階的テンプレートや支援ツールが必要であれば、それに即した設計もご提案可能です。必要であればご相談ください。
Claudeさんの見解
モデル情報:Claude Sonnet 4
答1(このキャラクターシートについて解説させる)
この設問群は、小説の登場人物に深い人間的リアリティと内面的整合性を与えるための体系的な人物設計システムですね。全体の意図と各設問の狙いを分析します。
全体の設計意図
この設問群は「人間の行動原理は過去の経験と他者との関係性によって形成される」という心理学的な前提に基づいて構築されています。表面的な設定ではなく、キャラクターの行動や選択に説得力のある動機を与え、読者が共感できる「生きた人物」を創造することを目的としています。
階層構造(A→a→b→c)により、最終的な目標から個人的な原体験まで、人格形成の因果関係を逆算的に設計できる仕組みになっています。
「人間の行動原理は過去の経験と他者との関係性によって形成される」という前提があるという指摘は大正解。私がシートに関連づけルールを取り入れた最大の理由です。
これが読み取れている時点で、関連づけルールの目的も各設問の意図も概ね理解できていると判断できます。
各設問の狙い
A【夢】: 物語全体を貫く主人公の核となる動機。他の全ての要素がここに収束する最上位目標として機能します。
a1【尊敬・軽蔑する人】: 価値観形成の起点となる重要他者の設定。この人物への感情が、主人公の行動指針や判断基準を決定づけます。
a2【自分の好きなところ】: 自己肯定感の源泉となる部分。困難に直面した時の精神的支柱や、成長の可能性を示す要素として機能します。
B【諦められないもの】: 主人公を突き動かす根本的な執着や価値観。物語中で最も重要な選択を迫られた時の判断基準となります。
b1【役に立ちたい人】: 利他的動機の対象。主人公の行動に社会性や他者性を与え、独りよがりでない魅力的なキャラクターにします。
b2【支えられている人】: 依存関係や感謝の対象。主人公の謙虚さや人間的弱さを表現し、完璧すぎないリアリティを生み出します。
b3【嬉しい想い出】: ポジティブな原体験。主人公の明るい面や希望的な行動原理の源泉となります。
b4【傷ついた記憶】: ネガティブな原体験。主人公の恐れや回避行動、あるいは乗り越えるべき課題の根源となります。
C【努力する理由】: 現状への不満や変革への意志。主人公を行動に駆り立てる直接的なエネルギー源です。
c1【広めたい思い】: 他者への積極的干渉の動機。主人公の社会的影響力や使命感を表現します。
c2【許せないこと】: 他者への否定的反応の動機。主人公の正義感や価値観の境界線を明確にします。
c3【感性が働く対象】: 個人的な美意識や興味関心。主人公の個性や専門性を際立たせる要素です。
c4【やりたいこと】: 純粋な個人的欲求。主人公の人間らしさや親しみやすさを演出する要素です。
この設問群の優れた点は、各要素が相互に関連し合い、矛盾のない一貫した人格を構築できることです。特に括弧内の参照関係により、表面的な設定と深層心理が論理的に結びつき、読者にとって理解しやすく説得力のあるキャラクターが完成します。
他の生成AI同様、やはりc3の出題意図は伝わっていません。
なまじ他の設問への理解が深いぶん、最後までここの誤解が足を引っぱります。
答2(作例を見たうえで改めて評価させる)
この作例は設問群の意図に非常によく適合しており、登場人物設計システムとしての有効性を実証する優れた例だと評価できます。
設問意図との適合性
階層構造の機能: A(夢)からc(個人的体験)まで、各設問の回答が論理的に連鎖しています。特に「自分を大切にできる人」という最終目標が、記憶喪失(b4)→自己否定→他者への献身→結果的な自己肯定という複雑な心理構造から自然に導出されている点が秀逸です。
参照関係の活用: 括弧内の指定通り、下位設問の組み合わせが上位設問を形成しています。例えばc2(判断を迫る人が嫌い)がb1(頼まれ事は断らない)とb4(くだらない記憶への自己嫌悪)から論理的に構築されており、表面的な設定と深層心理が見事に結びついています。
システムの効果的機能について
内的整合性: 一見矛盾する要素(怠惰だが勤勉、他人に干渉されたくないが献身的)が、深層の動機によって統一的に説明されています。これにより読者が理解しやすい複雑な人格が実現されています。
行動原理の明確化: 各場面での行動選択(危険な突撃、道化の演技など)が、設定された心理構造から必然的に導かれており、キャラクターの予測可能性と意外性のバランスが取れています。
成長可能性の内蔵: 現在の状態(自己否定)と目標(自己肯定)の間に明確なギャップがあり、物語を通じた変化の余地が十分に確保されています。
設定の過不足について
十分にカバーされている要素:
- 過去のトラウマと現在の行動の因果関係
- 他者との関係性における複雑な感情
- 表面的行動と内面的動機の乖離
- 成長への道筋と障害
補強できる要素:
- 身体的・物理的制約: 記憶喪失以外の具体的な能力や限界
- 社会的立場の詳細: ブレイド隊員としての具体的な責任や権限
- 時間軸の設定: 記憶喪失からの経過時間や今後の見通し
特に優れている点
矛盾の統合: 「他人に干渉されたくないが他人のために働く」という根本的矛盾を、自己防衛メカニズムとして説得力を持って説明している点が卓越しています。
感情の段階性: c3(心配されることへの拒絶反応)からc4(命がけの献身)への感情の流れが、彼女の複雑な自己愛憎を巧妙に表現しています。
総合評価
この作例は設問群が意図した「論理的で説得力のある人格構築」を見事に達成しており、システムの有効性を証明しています。特に、表面的な行動と深層心理の乖離を一貫した動機で説明する手法は、現代的なキャラクター造形の要請に応えた優秀な設計です。
設問群自体も、この作例を通じて登場人物設計における必要十分な要素をカバーしていることが確認できます。強いて言えば、より具体的な能力設定や社会背景の項目があれば完璧ですが、現状でも実用的には十分機能していると判断できます。
やはり外的要素の不足は指摘されますね。これが既存アニメの考察だとブログの読者さんも基本的に視聴済みの人ばかりなので、なおさら説明する必要を感じにくいのですが。
答3(他の脚本理論と比較してもらう)
はい、主要な脚本術における登場人物設計手法について理解があります。比較分析を行います。
主要脚本術との比較
ハリウッド三幕構成系(シド・フィールド、ロバート・マッキーなど)
- 重視する要素: 外的目標、内的欲求、致命的欠陥、バックストーリー
- この設問群との違い: ハリウッド式は「物語を動かす力」を重視するのに対し、この設問群は「人格の論理的整合性」に特化している
キャラクター・アーク理論(リンダ・シーガーなど)
- 重視する要素: 変化前後の状態、変化を阻む内的障害、触媒となる出来事
- 共通点: A(夢)→現状のギャップが変化の余地を示している点
ジョセフ・キャンベルの英雄の旅
- 重視する要素: 旅路の各段階における役割、メンター、敵対者
- 不足している観点: 他キャラクターとの関係性定義が薄い
ChatGPTが出してきた表もよかったですが、これもすごいですね。比較にあたって複数の理論を分類しています。生成AIってここまでできるんですね。
この設問群の独自の強み
心理学的論理性の徹底
従来の脚本術が「劇的効果」を優先するのに対し、この設問群は人間心理の因果関係を重視。これにより、読者が「なぜこのキャラクターはこう行動するのか」を直感的に理解できる。
相互参照システム
設問同士の参照関係により、表面的設定と深層心理の矛盾を防ぐ仕組みが秀逸。従来手法では設定の整合性チェックは作家の技量に依存していた。
内向性キャラクターへの適応
ハリウッド式が外向的・行動的キャラクターを前提とするのに対し、この設問群は内省的・受動的キャラクターも自然に設計できる。
不足している観点
物語機能の欠如
- 問題点: キャラクターの物語内での役割(主人公、対立者、助言者など)を規定する項目がない
- 具体例: ミルストレアが主人公なのか、狂言回しなのか、この設問群からは判断できない
他者との関係性設計の浅さ
- 問題点: b1、b2で他者への言及はあるが、相互関係や力学の設計が不十分
- 改善案: 「このキャラクターにとって最大の脅威となる人物」「価値観が正反対の相手」などの設問が必要
外的制約・能力の軽視
- 問題点: 身体能力、社会的地位、経済状況など、行動を制限する要素への言及が薄い
- 影響: キャラクターの選択肢の幅が不明確になりがち
時系列設計の不備
- 問題点: 過去(b3、b4)と現在はあるが、未来への具体的展望が曖昧
- 改善案: 「3年後、5年後にどうなっていたいか」など時間軸を明確にする設問
少し上のところで「ハリウッド式が外向的・行動的キャラクターを前提とする」と語られているのがまさにこういうところですね。時系列設計以外の指摘事項が全部対人関係がらみです。
(実際、設定しておいたほうがいい部分ではあるんでしょうけど。ドラマって人と人との間に生まれるものですし)
重複・洗練されていない点
c1とc2の機能重複
c1(広めたい思い)とc2(許せないこと)は共に「他者への干渉」を扱っているが、分離の必然性が薄い。統合して「他者に対する価値観の押し付け方」として扱えるのでは。
B(諦められないもの)の抽象度
他の設問が具体的体験や人物を問うのに対し、Bだけが概念的すぎる。「心の平穏」のような抽象概念では、具体的行動指針につながりにくい。
a2(好きなところ)の設定根拠
(b3+b4+c3+c4)という参照が複雑すぎて、なぜこの組み合わせで自己評価が決まるのか論理的根拠が不明確。
これはc3の意図が伝わっていないせいですね。
改善提案
追加すべき設問
- 物語機能: 「この人物がいることで物語にどんな要素が加わるか」
- 外的制約: 「行動を制限する現実的要因」
- 関係性: 「最も対立する可能性の高い人物像」
- 能力・才能: 「他者より明らかに優れている/劣っている分野」
統合・簡略化案
- c1、c2を「他者への価値観投影」として統合
- Bをより具体的な「執着対象」に変更
- a2の参照構造を簡略化
総合評価
この設問群は人物の内面的整合性という点で既存脚本術を上回る優れたシステムですが、「物語を動かす装置としてのキャラクター」という観点が不足しています。心理的リアリズムと物語機能のバランスを取るため、上記の改善を加えることで、より完成度の高い人物設計システムになると考えられます。
答4(改善案を作成させてみる)
改良版キャラクター設計テンプレート
基本情報
人物名:
物語内役割: [ ] 推進者(主人公) [ ] 対立者 [ ] 助言者 [ ] 変革者 [ ] 狂言回し [ ] その他
第1階層:最終目標(物語の核心)
A【理想とする最終状態】(B+C+a1+a2)
この人物が物語の終わりまでに到達したい境地
- 内面的変化:
- 外面的変化:
- 人間関係の変化:
第2階層:価値観形成の源泉
a1【最も影響を受けた人物】(b1+b2+c1+c2)
価値観形成の起点となる重要他者
- 人物:
- 関係性:[ ] 尊敬 [ ] 軽蔑 [ ] 憧れ [ ] 恐怖 [ ] 複雑な感情
- 受けた影響:
a2【自分の核となる強み】(b3+c3)
困難時の精神的支柱となる自己肯定の源泉
- 能力・才能:
- 性格的特徴:
- これがあるから乗り越えられること:
a3【最大の弱点・制約】(b4+c4)
行動を制限する内的・外的要因
- 内的制約(恐怖、苦手意識):
- 外的制約(能力、立場、環境):
- これによって諦めざるを得ないこと:
第3階層:行動原理
B【絶対に手放せない価値】(b1+b2+b3+b4)
最終選択を迫られた時の判断基準
- 具体的な対象・概念:
- なぜそれが重要なのか:
- それを脅かす要因:
C【現状への不満・変革動機】(c1+c2+c3+c4)
行動を起こすエネルギー源
- 変えたい現実:
- 変革への具体的動機:
- 変化を阻む障害:
第4階層:人間関係(他者軸)
b1【最も貢献したい対象】
利他的行動の方向性
- 具体的な人物・集団:
- 貢献方法:
- その理由:
b2【依存している支援者】
精神的・物質的支えの源泉
- 具体的な人物・システム:
- 受けている支援:
- 失ったときの影響:
第5階層:個人史(経験軸)
b3【形成的なポジティブ体験】
現在の強みや希望の源泉となった出来事
- 具体的な出来事:
- 年齢・時期:
- 学んだこと・得たもの:
b4【形成的なネガティブ体験】
現在の恐怖や回避行動の源泉となった出来事
- 具体的な出来事:
- 年齢・時期:
- 失ったもの・学んだこと:
第6階層:行動パターン(具体的発現)
c1【他者への積極的働きかけ】(b2+b3)
社会に対する建設的な影響力
- 広めたい価値観:
- 実際の行動:
- 期待する反応:
c2【他者への拒絶反応】(b1+b4)
社会に対する防御的な反応
- 許せない行為・価値観:
- 実際の対処法:
- 妥協できない理由:
c3【個人的なこだわり・美意識】(b1+b3)
個性や専門性を際立たせる要素
- 特に敏感に反応する分野:
- 具体的な基準・好み:
- そこに込めた意味:
c4【純粋な個人的欲求】(b2+b4)
他者とは無関係な私的動機
- やりたいこと:
- 欲しいもの:
- そうする理由:
第7階層:物語機能
D【物語内での役割・機能】
他キャラクターや物語展開に与える影響
- 主人公に与える影響:
- 物語に持ち込む要素:
- 不在になったときの物語への影響:
E【対立・協力関係】
主要な人間関係の力学
- 最も対立する可能性の高い人物像:
- 最も協力関係を築きやすい人物像:
- その理由:
補完情報
能力・制約
- 優れている分野:
- 劣っている分野:
- 社会的立場・権限:
- 経済状況:
- 身体的特徴・制約:
時系列設計
- 過去の重要な転換点:
- 現在の状況:
- 3年後の理想像:
- 最終的な到達点:
言動パターン
- 口癖・特徴的な表現:
- 特徴的な行動:
- ストレス時の反応パターン:
- 他者からの典型的な評価:
設問間の参照関係チェック
□ A(理想状態)がB+C+a1+a2から論理的に導出されている
□ a1(影響人物)がb1+b2+c1+c2の経験から必然的に生まれている
□ a2(強み)がb3+c3のポジティブ要素から構成されている
□ a3(弱点)がb4+c4のネガティブ要素から構成されている
□ B(核となる価値)が4つのb要素すべてに支えられている
□ C(変革動機)が4つのc要素すべてに支えられている
□ 各c要素が指定されたb要素の組み合わせから導出されている
□ D・E(物語機能)が全体の設定と矛盾していない
一貫性確認質問
- このキャラクターの最も重要な選択場面で、どう行動するか予測できるか?
- 表面的な行動と内面的動機に納得できる説明があるか?
- 他のキャラクターとの関係で、独自の価値を発揮できるか?
- 成長・変化の余地と方向性が明確か?
- 読者/視聴者が共感または理解できる要素があるか?
これ、すっごい出来がいいと思いません? クソ長いけど!!
基本情報から網羅してありますし、キャラクターアークやストーリーとの接合もバッチリ押さえてあります。それでいて私オリジナルの関連づけルールも生かしてくれています。
何よりすばらしいのが、これ、あんまり脚本理論に詳しくない人でもシートを読むだけでどういうキャラクターなのか全体像を俯瞰できる構成になっていることです。
たぶん、アニメとかゲームとか、複数人で手分けして物語を考える現場で活用すれば絶大な効果を発揮するんじゃないでしょうか。私にそういう業界とのコネは無いけども! モドカシイ!!
この改良版テンプレートの主な改善点を説明します:
追加された要素
物語機能の明確化
- 冒頭で物語内役割を選択式で指定
- D【物語内での役割・機能】で他キャラクターとの相互作用を設計
- E【対立・協力関係】で人間関係の力学を明確化
制約条件の具体化
- a3【最大の弱点・制約】を新設し、内的・外的制約を分離
- 「能力・制約」セクションで社会的・身体的・経済的制約を明記
- 行動選択の現実的限界を設定可能
時系列設計の強化
- 過去・現在・未来の連続性を明確化
- 3年後の理想像で中期目標を設定
- 最終到達点で長期ビジョンを明確化
構造の改善
参照関係の最適化
- a2(強み)をb3+c3に簡略化し、ポジティブ要素に集約
- a3(弱点)をb4+c4に設定し、ネガティブ要素に集約
- 論理的整合性を保ちながら複雑さを軽減
チェック機能の充実
- 設問間参照関係の確認リスト
- 一貫性確認質問で設計品質を検証
- 作成後の見直しを体系化
実用性の向上
選択式項目の導入
- 物語役割、人物への感情など、選択肢で迷いを軽減
- より具体的で使いやすい形式
補完情報の体系化
- 言動パターンで表現上の特徴を明記
- 他者からの評価で客観的視点を追加
この改良版は、元の設問群の心理的整合性という強みを保ちながら、脚本術で重視される物語機能と実用性を大幅に強化したものです。特に、内面の論理と外面の役割のバランスを取ることで、より完成度の高いキャラクター設計が可能になります。
答4.1(改善案を使っての作例をつくらせてみる)
ちょっとびっくりするくらい改善案の出来がよかった(そしてヘビー級すぎて書きかたがイマイチピンとこなかった)ので、具体的な作例を見せてもらうことにしました。
こちらからの質問は「この改良版キャラクター設計テンプレートに先ほどの「ミルストレア」を当てはめて作例を提示してください。情報が無い部分は適宜創作して構いませんが、どの部分を創作したか明確にわかるようにしてください。」でした。
ミルストレア設計例(改良版テンプレート適用)
基本情報
人物名: ミルストレア
物語内役割: [✓] 推進者(主人公) [ ] 対立者 [ ] 助言者 [ ] 変革者 [ ] 狂言回し [ ] その他
第1階層:最終目標(物語の核心)
A【理想とする最終状態】(B+C+a1+a2)
この人物が物語の終わりまでに到達したい境地
- 内面的変化:自分を大切にできる人。自分の命を安く叩き売ることをやめ、生きていることに価値を見出せるようになる
- 外面的変化:【創作】自動販売機的な存在から脱却し、個人として他者と向き合えるようになる
- 人間関係の変化:他者からの干渉を受け入れ、相互的な関係を築けるようになる
第2階層:価値観形成の源泉
a1【最も影響を受けた人物】(b1+b2+c1+c2)
価値観形成の起点となる重要他者
- 人物:ヒメリ・アランジ(同僚のコンパニオン)
- 関係性:[✓] 尊敬 [ ] 軽蔑 [✓] 憧れ [ ] 恐怖 [✓] 複雑な感情
- 受けた影響:人のために誠心誠意尽くすという理想像を示している。自分にはできないと思いながらも、そのあり方を強く尊敬している
a2【自分の核となる強み】(b3+c3)
困難時の精神的支柱となる自己肯定の源泉
- 能力・才能:従順さ、指示に従う能力、【創作】異常なまでの任務遂行能力
- 性格的特徴:争いを避ける平和主義、寛容性
- これがあるから乗り越えられること:人間関係のトラブルを回避し、与えられた役割を確実に果たせる
a3【最大の弱点・制約】(b4+c4)
行動を制限する内的・外的要因
- 内的制約(恐怖、苦手意識):自分で判断することへの恐怖、個人的な関心を探られることへの嫌悪感
- 外的制約(能力、立場、環境):記憶喪失による過去の欠如、【創作】コンパニオンとしての公的立場
- これによって諦めざるを得ないこと:自分らしい生き方、個人的な野心や夢
第3階層:行動原理
B【絶対に手放せない価値】(b1+b2+b3+b4)
最終選択を迫られた時の判断基準
- 具体的な対象・概念:心の平穏、何も考えずに生きられる状態
- なぜそれが重要なのか:自分自身への関心を持つことが苦痛だから
- それを脅かす要因:自己判断を迫る状況、個人的な感情を問われること
C【現状への不満・変革動機】(c1+c2+c3+c4)
行動を起こすエネルギー源
- 変えたい現実:他人に干渉されること、個人として注目されること
- 変革への具体的動機:自動販売機のような存在になりたい、便利に使われても個体として興味を持たれたくない
- 変化を阻む障害:エルマとリンの存在、任務で関わる人々の親切や心配
第4階層:人間関係(他者軸)
b1【最も貢献したい対象】
利他的行動の方向性
- 具体的な人物・集団:頼みごとをしてきた人たち、任務で出会う市民
- 貢献方法:与えられた任務を確実にこなす、パトロールで困っている人を見つける
- その理由:頼まれごとを断るのが面倒くさいから、拒否することすら面倒
b2【依存している支援者】
精神的・物質的支えの源泉
- 具体的な人物・システム:エルマとリン(共同生活のルームメイト)
- 受けている支援:生活リズムの維持、勤務態度の監視効果
- 失ったときの影響:極限まで堕落してしまう、サボり癖が加速する
第5階層:個人史(経験軸)
b3【形成的なポジティブ体験】
現在の強みや希望の源泉となった出来事
- 具体的な出来事:任務報告をして感謝されること、人の笑顔を見ること
- 年齢・時期:【創作】コンパニオンとして働き始めてから継続的に
- 学んだこと・得たもの:他人の喜びを見ることへの素直な嬉しさ、パトロール自体は嫌いではないという発見
b4【形成的なネガティブ体験】
現在の恐怖や回避行動の源泉となった出来事
- 具体的な出来事:記憶喪失で目覚めた時、自分の名前より漫画のキャラクター名の方を覚えていたこと
- 年齢・時期:【創作】現在から約2年前(記憶の始まり)
- 失ったもの・学んだこと:過去の自分への呆れと軽蔑、自分の価値への疑問
第6階層:行動パターン(具体的発現)
c1【他者への積極的働きかけ】(b2+b3)
社会に対する建設的な影響力
- 広めたい価値観:誰もが寛容であってほしい、他人に興味を持たないでほしい
- 実際の行動:異種族・異星人・機械に対しても地球人類と同じ態度で接する
- 期待する反応:相手も自分に特別な関心を持たず、淡々とした関係を築くこと
c2【他者への拒絶反応】(b1+b4)
社会に対する防御的な反応
- 許せない行為・価値観:自分で判断するよう迫ってくること、画一的対応を嫌がること
- 実際の対処法:ひどく動揺する、ギリギリまで答えを避ける
- 妥協できない理由:自分なりの答えを持っていることがバレるのが嫌、本音を隠しておきたい
c3【個人的なこだわり・美意識】(b1+b3)
個性や専門性を際立たせる要素
- 特に敏感に反応する分野:自分のことを心配する人への反応
- 具体的な基準・好み:好かれることは嫌いじゃないが、心配されるのだけは嫌
- そこに込めた意味:内面を探られることへの恐怖、汚らしい本性を見られたくない
c4【純粋な個人的欲求】(b2+b4)
他者とは無関係な私的動機
- やりたいこと:自分にできることなら何でも、たとえ命がけでも
- 欲しいもの:面倒くさい仕事を今すぐ完遂できる方法
- そうする理由:自分の命なんて安いもの、早く任務を終わらせたい
第7階層:物語機能
D【物語内での役割・機能】
他キャラクターや物語展開に与える影響
- 主人公に与える影響:【創作】自己犠牲と自己肯定のテーマを体現、仲間たちに「命の価値」について考えさせる
- 物語に持ち込む要素:内面と外面の乖離による複雑性、記憶喪失というミステリー要素
- 不在になったときの物語への影響:【創作】チームの異常な任務遂行能力が失われる、エルマとリンが彼女の本当の気持ちに気づくきっかけが失われる
E【対立・協力関係】
主要な人間関係の力学
- 最も対立する可能性の高い人物像:【創作】個人の内面や本音を暴こうとする心理分析者タイプ、強制的に自己決定を求める権威主義者
- 最も協力関係を築きやすい人物像:指示を明確に出してくれる上司、表面的な関係を維持してくれる同僚
- その理由:自分のペースで働ける環境と、深く踏み込まない人間関係を好むため
補完情報
能力・制約
- 優れている分野:【創作】任務遂行能力、危険察知能力、異文化対応力
- 劣っている分野:自己決定、感情表現、個人的な人間関係の構築
- 社会的立場・権限:ブレイド隊員、コンパニオン、【創作】一般隊員レベル
- 経済状況:【創作】公務員としての安定収入、エルマ・リンとの共同生活
- 身体的特徴・制約:【創作】記憶喪失以外の身体的制約は特になし、戦闘能力は標準以上
時系列設計
- 過去の重要な転換点:記憶喪失からの覚醒、ナギ長官からの採用、エルマチームへの配属
- 現在の状況:自己否定的だが高い業務能力を持つコンパニオンとして活動中
- 3年後の理想像:【創作】自分の価値を認め、他者との適切な距離感を保てる人
- 最終的な到達点:自分を大切にしながらも他者に貢献できるバランスの取れた人格
言動パターン
- 口癖・特徴的な表現:【創作】「面倒くさい」「ダルい」、皮肉めいた自虐的発言
- 特徴的な行動:道化を演じる、本音をぼかす、危険な任務に率先して向かう
- ストレス時の反応パターン:動揺して逃避的になる、より一層道化めいた発言をする
- 他者からの典型的な評価:【創作】「変わり者だが頼りになる」「本心がよくわからない」「なぜか放っておけない」
設問間の参照関係チェック
☑ A(理想状態)がB+C+a1+a2から論理的に導出されている
☑ a1(影響人物)がb1+b2+c1+c2の経験から必然的に生まれている
☑ a2(強み)がb3+c3のポジティブ要素から構成されている
☑ a3(弱点)がb4+c4のネガティブ要素から構成されている
☑ B(核となる価値)が4つのb要素すべてに支えられている
☑ C(変革動機)が4つのc要素すべてに支えられている
☑ 各c要素が指定されたb要素の組み合わせから導出されている
☑ D・E(物語機能)が全体の設定と矛盾していない
一貫性確認質問
- このキャラクターの最も重要な選択場面で、どう行動するか予測できるか?
→ Yes. 自分の命を犠牲にしてでも任務を完遂しようとするが、それを心配する仲間の存在が彼女を思いとどまらせる構図が予測できる - 表面的な行動と内面的動機に納得できる説明があるか?
→ Yes. 怠惰そうに見えて勤勉、他人を拒絶したいのに献身的という矛盾が、記憶喪失による自己否定から論理的に説明されている - 他のキャラクターとの関係で、独自の価値を発揮できるか?
→ Yes. エルマ・リンとの対比、ヒメリへの複雑な感情、上司や市民への独特な接し方で個性を発揮 - 成長・変化の余地と方向性が明確か?
→ Yes. 自己否定から自己肯定への変化、他者との関係性の改善という明確な成長軸がある - 読者/視聴者が共感または理解できる要素があるか?
→ Yes. 自己肯定感の低さ、他者との距離感の難しさ、過去のトラウマなど現代的な悩みと共通点がある
ちゃんと書いてくれるものですね。
これだけやってくれるならもうひとつ使い道が考えられます。
キャラクターについての考察を思いついた端から羅列したメモ書きを渡して、このキャラクターシートの様式を渡せば、それだけでこんなにもわかりやすくアイディアを整理してくれるわけですよ。どのあたりの掘り下げが甘いか自分で俯瞰することすらできちゃうわけですよ。自分じゃこんなクソ長いシート絶対書きたくないのに!
これはちょっと・・・、Claudeさんに書かせるためのキャラクターシートを本気で開発してみる価値あるかもですね。
【創作部分の明示】
【創作】マークを付けた部分:
- 外面的変化の具体的描写
- 異常な任務遂行能力の設定
- コンパニオンとしての公的立場の制約
- 記憶喪失の時期設定(2年前)
- 物語機能での他キャラクターとの関係性詳細
- 対立・協力関係の具体的人物像
- 能力・制約の詳細設定
- 3年後の理想像と最終到達点
- 言動パターンの具体的表現
- 他者からの評価
この作例では、元のミルストレアの設定を改良版テンプレートに当てはめ、不足していた情報を創作で補完しました。
主な改善効果
物語機能の明確化
元の作例では曖昧だった「ミルストレアが物語にどんな影響を与えるか」が明確になりました。特に仲間たちに「命の価値」について考えさせる触媒としての役割が明確化されています。
制約条件の具体化
「記憶喪失」という設定が単なる背景から、行動を制限する具体的要因として機能するようになりました。また、コンパニオンという立場の制約も明確化されています。
時系列の整理
記憶喪失から2年という設定により、現在の状況と将来への展望が整理され、キャラクターの成長可能性がより具体的になりました。
他者との関係性の深化
元作例では個人的な内面に焦点が当たっていましたが、エルマ・リンとの共依存関係、ヒメリへの複雑な感情などが体系的に整理され、人間関係の力学が明確になりました。
創作部分の方針
創作した部分は、元の設定と矛盾しないよう注意深く設計しています。特に:
- 能力設定:元作例の「異常なまでの任務遂行能力」を裏付ける設定
- 時間軸:記憶喪失から2年という現実的な期間設定
- 成長目標:元の「自分を大切にできる人」という目標をより具体的な段階に分解
- 言動パターン:元作例の「道化を演じる」行動をより体系的に整理
この改良版により、ミルストレアというキャラクターの内面的複雑さを保ちながら、物語内での機能と他キャラクターとの関係性が格段に明確化されました。
答5(キャラクター設計にかかる所要時間の予想)
初学者が元の設問群を使ってミルストレア程度のキャラクター設計を行う場合の所要時間を、段階別に分析してみます。
段階別所要時間の推定
第1段階:設問群の理解(30-60分)
- 設問の意味と相互関係の把握
- 参照構造(A+B+a1+a2など)の理解
- 具体的にどの程度詳しく書けばいいかの判断
第2段階:基本コンセプトの決定(1-2時間)
- キャラクターの大まかな方向性決定
- A【夢】の設定(最も重要で時間がかかる部分)
- 基本的な性格や立場の決定
第3段階:下位設問の回答(3-5時間)
- b1-b4(具体的体験)の設定:1.5-2時間
- c1-c4(行動パターン)の設定:1.5-2時間
- 各設問間の整合性確認:1時間
第4段階:上位設問との整合性調整(2-3時間)
- a1、a2(価値観形成)の調整
- B、C(行動原理)の調整
- 全体の論理的一貫性の確認
第5段階:文章化と推敲(2-4時間)
- 各設問の回答を説得力のある文章にまとめる
- 矛盾点の発見と修正
- 最終的な調整
総所要時間:8.5-15時間
最初にAを書けとは無茶をおっしゃいますが、・・・よくよく考えてみたらAはそのキャラクターの一番の核心なんですから、(既存作品の考察でできるかはさておき)オリジナルキャラクターの設計でなら案外できちゃうかもしれないですね。一番最初に思いつくアイディアでしょうから。
関連づけは後で考えたらいいんです。ゴールから逆算して過去の出来事を考えてやるって方法も当然できるわけで。
現実的な作業パターン
集中的に取り組む場合:2-3日
- 1日目:4-5時間(理解+基本コンセプト+下位設問の一部)
- 2日目:4-5時間(下位設問完成+整合性調整)
- 3日目:2-3時間(文章化+推敲)
断続的に取り組む場合:1-2週間
- 毎日1-2時間ずつ作業
仕事かな?
初学者特有の困難要因
時間を要する部分
- 設問間の論理的整合性の構築(最大の難所)
- 抽象的な概念(B「諦められないもの」など)の具体化
- 参照関係の理解と実践
- 矛盾のない人格の構築
つまずきやすいポイント
- 「こうなりたい夢」が漠然としすぎて具体化できない
- b3、b4の体験設定で、現在の性格との因果関係を作れない
- c1-c4の行動パターンが表面的になりがち
- 全体として「なぜこのキャラクターはこう行動するのか」の説明力不足
効率化のための推奨アプローチ
段階的作成法
- まず粗く全項目を埋める(3-4時間)
- 下位から上位へ整合性を確認(2-3時間)
- 文章を整える(2-3時間)
初学者向けの時短技法
- 既存のキャラクター(小説、映画、アニメ)を参考にする
- 自分の経験や知人をモデルにする
- 最初から完璧を目指さず、「6割の完成度で一度完成させる」
習熟による時短効果
2回目以降の作成時間
- 2-3回目:6-10時間(理解時間の短縮)
- 5回目以降:4-6時間(パターンの習得)
- 10回目以降:2-4時間(熟練者レベル)
結論
初学者がミルストレア程度の完成度を目指す場合、現実的には10-12時間程度を見込むべきでしょう。これは決して短い時間ではありませんが、従来の「なんとなくキャラクターを作る」方法と比べて、格段に論理的で説得力のあるキャラクターが完成するため、投資効果は十分に高いと考えられます。
特に重要なのは、「一度に完成させようとしない」ことです。初学者は6-7割の完成度で一度形にし、後から改善していく方が効率的で挫折しにくいでしょう。






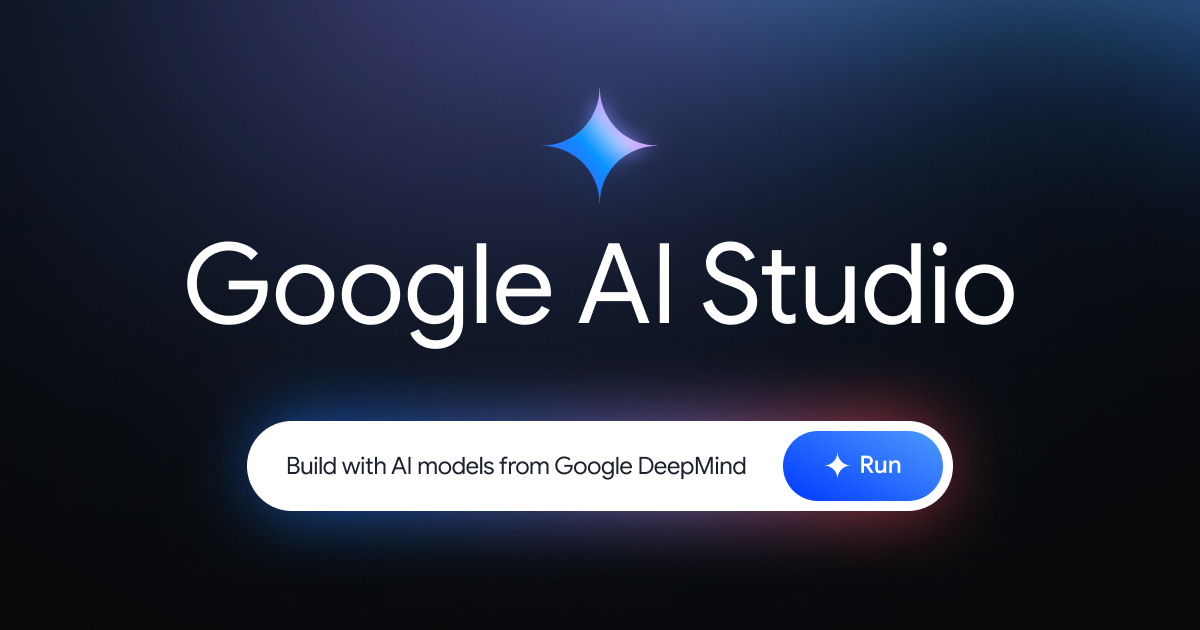


コメント